
Writer:鈴木陸夫
2025/09/26
SalesPlus関晋弥氏対談「未来の小売店舗、三方よしの顧客体験」:後編
前編に引き続き、株式会社SalesPlusの関晋弥代表取締役副社長COOと、セーフィー代表取締役社長CEOの佐渡島による対談をお届けします。小売業界が直面する課題と、デジタルが持つ変革の可能性を概観した前編、後編では小売、メーカー、消費者の「三方よし」をどう実現していくのか、さらに深掘りしていきます。
<前編記事はこちら>
ライバル同士が手を取り合うことで生まれる可能性
佐渡島
SalesPlusさんは2023年9月に「九州リテールメディア連合会」を立ち上げていらっしゃいます。競合の関係にある九州地域の小売各社が連携して、業界全体の課題解決を目指すものと伺っております。非常に画期的な取り組みだと思いますが、これはどのような経緯で立ち上がったのでしょうか?

関
冒頭でも申し上げましたが、私の根本には、リテールメディアの力を信じる気持ちがあります。テレビやデジタル広告ももちろん素晴らしいメディアではありますが、お買い物の現場により近いところにあるリテールメディアが増えることにより、お客さまのお買い物体験をより豊かなものにすることができるでしょう。また、商品をレコメンドしたいと考えているメーカーさんもお喜びになるでしょうし、売上が伸びれば、もちろん小売店舗も嬉しいです。そのような形でWin-Win-Winが成り立つのがリテールメディアだと考えています。
私としては、このリテールメディアを広げていきたいと思っており、そのために構想したのが、複数の小売を跨いだリテールメディアのネットワークです。
加盟いただいている小売企業同士は、おっしゃる通り、九州では激しいライバル関係にあります。しかし、ことリテールメディアに関して申し上げれば、競合というより、むしろ共創の領域なのではないかと考えています。安心安全な店舗運営のあり方やごみ削減といった問題は、ライバル関係を超えて協働で解決していくべき問題だと考えますが、リテールメディアも同様に、業界全体を発展させるため、手を取り合ってやっていくべき領域ではないか。各社に向けてそのような説明をしたところ、思っていた以上に賛同していただくことができました。
佐渡島
ライバル同士が垣根を超えて九州全体で変革を起こせたら、そのインパクトは大きなものになるでしょうね。具体的にはどのような活動をされていますか?
関
デジタルということからは少し離れてしまいますが、スーパーにおいて、メーカー、お客さまとの重要な接点となるのが「陳列棚」です。我々はサイネージやアプリだけではなく、棚そのものがメディアだと考えています。

そういう意味でご紹介したいのが、弊社が九州の小売各社さんと行っている、風除室に関する取り組みです。風除室というのは、店舗に入ってすぐの位置にある、外からの冷気や熱気を遮断するための空間のこと。この風除室をメディアと捉え、そこにさまざまなメーカーの商品を陳列することで、売上にどれだけ変化があるかという実験を行っています。
結論から言うと、前年同期比で売上300%アップといった目覚ましい成果が出ている事例も出てきています。
佐渡島
それは素晴らしいですね!
関
本当にたくさんのメーカーさんから引き合いがあるのですが、とあるお菓子メーカーさんが昨年、この「風除室のメディア利用」を3回実施してくれました。一度目は工場の生産能力の問題で欠品も起こしてしまいましたが、二度目はその教訓を活かし、あらかじめ在庫や製造のキャパシティーを増やしてもらったおかげで、かなり売上を伸ばすことができました。けれども、三度目はお客さまの飽きもあったのか、二度目の成果を超えることができませんでした。
いまはまだ知見が溜まりきっていないため、前回の経験くらいしか参考にできるものがなく、こういう失敗も起こり得ます。しかし、今後十分に知見が溜まっていけば、もっと精度高く製造の量や期間を調整することも可能になるだろうと見ています。
佐渡島
我々はファストファッション業界の大手企業さんともお付き合いがありますが、同社が強いのは、製造から販売までをワンストップでやれているからです。それゆえスピード感を持って上流から下流までを最適化できるわけです。

たくさんの取引先の商品が並ぶスーパーで同じことはできませんが、いままさにご紹介いただいたように、一部の棚に絞って、メーカーさんと組んで実験を行うことならできるはず。その結果を元に生産量のコントロールができれば、メーカーにとってもありがたいでしょう。さらに、ライバル同士でその知見を共有できると、生み出せるインパクトは相当大きなものになるのではないでしょうか。
「デジタル店長」が買い物体験をワクワクさせる
佐渡島
一方、お客さまの購買体験は今後、どのようにワクワクするものへと変えていけるでしょうか。
関
トライアルさんから伺って面白いと思った表現に「サイネージとはデジタル店長である」というものがあります。
八百屋さんのように扱っている商品点数がそれほど多くなければ、店長がすべての商品に関して背景を把握し、お客さまに説明することもできるでしょう。しかし、トライアルさんのように店舗あたりの商品点数が数万SKU(Stock Keeping Unit)という規模になると、それは不可能です。
そこに「デジタル店長」としてのサイネージへの期待があります。コーナーごとに設置されたサイネージがそのコーナーの「店長」の役割を果たし、担当する商品の背景をお客さまに伝えることができたら、それはお客さまにとっての楽しい、ワクワクする購買体験につながっていくのではないでしょうか。
佐渡島
なるほど。

関
さらに言えば、八百屋さんが私に対して勧める商品と、上品なご夫人に対して勧める商品はおそらく違います。長年の経験や勘に基づいて、相手の身なりや容姿、年代によって接客を変えていますよね。デジタルサイネージは、いまのところは誰に対しても画一的なコンテンツを流しています。しかし、カメラでお客さまを判別し、それに応じて流すコンテンツを変えるといったことができれば、同じ一枚のモニターであっても、購買効果を絶対に向上させられるはずです。
佐渡島
そこに生成AIのようなインタラクションがあると非常に面白いですね。
私の家の冷蔵庫には、常に「ピエトロドレッシング」が3本あります。スーパーへ行って、売っているのを見るたびに、つい買いたくなってしまう。「あれだけ食べたし、もう切らしているだろう」と思って、見る度に買ってしまうのです。
「誰かがストックあるよと忠告してくれればいいのに」と思うのですが、とはいえ、冷蔵庫の中身をすべて誰かに把握されているというのは、さすがに気味が悪い。しかし、毎日買い物に訪れるスーパーの「店長」が、自然な会話の中で教えてくれるのだったらどうでしょうか。POSデータに基づいて「2週間前に買っていましたよ」と教えてくれたら、私だったら非常にありがたいと思います。
あるいは、ブロックの牛肉を買っても、使いきれずに無駄にしてしまうことがあります。そんなとき、購買データを元に「今日はシチューにしてみてはいかがですか?」と提案してもらえるのも大変助かります。それは面白い購買体験として、多くの人にも受け入れてもらえるのではないでしょうか。
目的を素早く果たすための、無人コンビニのような世界観も一方にはあっていいと思いますが、「デジタル店長」と会話をしながら買い物をするといったことができると、それは欲しい未来だなと思います。

行動が広がっていくようなデジタル活用を
佐渡島
これまでの小売業界におけるデータの活用は、データから勝ち筋を見出し、それを各店舗に横展開することで効率化する、といったものだったと思います。ですが、一消費者目線で考えると、そうやってどの店も同じになっていくのは、どうも面白くありません。
私は普段、ギリシャヨーグルトは成城石井で買いますが、サラダに関してはコンビニで買う、といった購買行動をしています。そういう私からすると、地域ごと、店舗ごとにそれぞれ異なる特徴を持っていてほしい。これからの小売は、そうやって購買行動が多様化するような方向に進化していってほしいなと思います。
関
小売企業にもコンビニ、ドラッグストアなどいくつかの業態がありますが、その中でも最も地場に根付いているのがスーパーマーケットだと思います。
その土地の魚、野菜、お米を扱っているというのがスーパーの強みであり、北海道と九州では美味しいものが違いますから、一つのフォーマットで全国統一しようとしても難しい。だからこそ、コンビニやドラッグストアのようにはスーパーの統廃合が進んでいないのかもしれません。そうだとすると、スーパーはなおさらエリアごとに押していく商品を変えていくべきでしょう。
エリア特性に応じて訴求を変えていくというのは、デジタルが最も得意とすることでもあります。リテール領域におけるDXは、コンビニやドラッグストア以上に、実はスーパーマーケットでこそ効いてくるのではないかと思いました。

佐渡島
同じサイネージでも、「これを買うべき」など一人一人の行動を縛る方向に使うのは古い。先ほどの「デジタル店長」との対話のように、行動が広がっていくような体験作り、お店作りにデジタルを活用できると、ワクワクしますし、面白くなっていくでしょうね。
関
同感です。「デジタル」と言うと、人の温かみがなくなると捉える人もいますが、私はむしろ逆だと思っています。人の温かみが少しずつ薄れつつある世の中にあって、デジタルを積極的に活用していくことで、お買い物の中にもう一回楽しさが返ってくるとか、気づきもしなかった商品との出会い、豊かさの拡張のようなことだって実現できるはず。人の一生が80年とすると、私は残された40年をそういうことに使っていきたいと思っています。
佐渡島
お客さま視点に立つとこんなにもワクワクする可能性が広がるということを改めて確認できて、今日はとても楽しかったです。ありがとうございました!

著者紹介 About Writer

- 鈴木陸夫
- フリーライター。よりよく生きるとはなにかを学び、実践し、還元したいとの思いで、ジャンルは問わず幅広く取材しています。
この連載について About Serial
「見える」未来を対談する
『見える』が拓く未来について、セーフィーCEO
佐渡島隆平が各界オピニオンリーダーと対話を深めます。
-
01

佐渡島庸平氏(コルク)対談 「世の中によき「目」が浸透すれば、 21世紀の人の生活が、一挙になめらかになるんだね!」
セーフィー代表の佐渡島隆平と、主にコンテンツ制作の世界で活動するエージェンシー「コルク」代表の佐渡島庸平は、名字を同じくするところから察せられる通り、じつは従兄弟同士なんです。同世代であることも手伝って、小さいころからと...
-
02
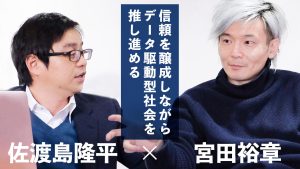
宮田裕章氏対談「日本流のデータ駆動型社会を実現するには『映像データ』がカギとなる」
医療の分野でデータを活用し次世代ヘルスケア改革に取り組む宮田裕章さん。今回は宮田さんの研究所におじゃまし、佐渡島と宮田さんそれぞれが描く「データ駆動型社会」を語ります。 宮田裕章さん2003年3月東京大学大学院医学系研究...
-
03
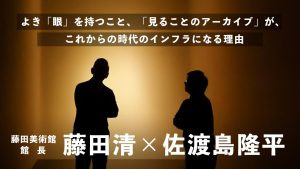
藤田清氏(藤田美術館館長)対談 「 よき『眼』を持つこと、『見ることのアーカイブ』が、 これからの時代のインフラになる理由」
収蔵品数は国宝9件と重要文化財53件を含むおよそ約2,000件。大阪にある藤田美術館は、古くからその名を広く轟かせています。現在はリニューアル期に入っている館に、藤田清館長を訪ねました。セーフィー代表・佐渡島と藤田館長に...
-
04

キヤノンMJ足立正親氏対談「映像が切り拓く未来へ、思いと人間力が紡いだ8年間の共創の軌跡」:前編
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)とセーフィー株式会社(以下、セーフィー)の関係は2017年の資本業務提携からスタートし、その後も映像データの利活用を軸に、さまざまな形でパートナーシップを深めて...
-
05

キヤノンMJ足立正親氏対談「両者が見据える「想像を超えた未来」。社会課題解決に映像はどう寄与できるか」:後編
前編に引き続き、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)代表取締役社長・足立正親さんとセーフィー株式会社代表取締役社長CEO・佐渡島による対談をお届けします。後編では、両者が映像データ活用で見据える「...
-
06

SalesPlus関晋弥氏対談「リテールメディアは小売の課題を解決できるか」:前編
九州に本社を置く小売企業トライアルホールディングス(以下、トライアル)は、業界の変革を目指し、お客さまの快適なお買い物体験につながるデジタルサイネージやレジカートなどのリテールメディア、さらには安心安全な店舗運営にむけて...