
Writer:鈴木陸夫
2025/09/26
SalesPlus関晋弥氏対談「リテールメディアは小売の課題を解決できるか」:前編
九州に本社を置く小売企業トライアルホールディングス(以下、トライアル)は、業界の変革を目指し、お客さまの快適なお買い物体験につながるデジタルサイネージやレジカートなどのリテールメディア、さらには安心安全な店舗運営にむけてセーフィーのカメラを導入するなど、多岐にわたる先進的な取り組みをされています。
そこで、今回はトライアルと電通の共同出資会社(※1)である株式会社SalesPlusの関晋弥代表取締役副社長COOと、セーフィー代表取締役社長CEOの佐渡島による対談が実現しました。リテールメディアの可能性を追求するSalesPlusの視点から見た、小売業界が直面する課題とは。映像・データ・デジタルの力を活用することで、どのようなワクワクする未来を創造できるか。両者によるディスカッションの模様を前後編でお届けします。
(※1)株式会社トライアルホールディングスのシステム子会社で、レジカートやサイネージシステムの開発を行うトライアルグループのリテールRetail AI社と、株式会社電通グループによる共同出資

夢はリテールメディアの可能性を広めること
佐渡島
本日は、映像やデータの力で小売業界の未来をどのようにワクワクするものにしていけるかについて、ざっくばらんにお話しできればと思っております。最初に関さんご自身についてお伺いしたいのですが、関さんはどういう経緯でSalesPlusの代表に就任されたのですか?
関
私自身の前に、SalesPlusという会社について簡単に説明させてください。SalesPlusは九州を中心に展開する小売企業・トライアルさんと電通が共同出資して作った会社です。より正確に言うなら、株式会社トライアルホールディングスのシステム子会社で、レジカートやサイネージシステムの開発を行うRetail AI社と、株式会社電通グループによる共同出資になります。社員数はまだ20人ほどで、売上も今年ようやく数億円といった小さな会社です。
商号をSalesPlusに変更したのは2020年です。前身はトライアルと電通の頭文字をとったT&Dという会社でした。現在はリテールメディアを中心とした事業に変わっていますが、2018年にT&Dとして創業した当初の目的は、実は「カメラデータのマーケティング活用について共同研究する」というものだったのです。トライアルさんのとある店舗に約700台のカメラを導入し、そこから得られるデータの活用について研究していました。
佐渡島
そうなんですか!
関
私自身は2007年に電通に入社し、主にコミュニケーションプランナーとしてのキャリアを歩んでまいりましたが、この会社が立ち上がったタイミングで代表取締役社長に就任しました。
ただ、私の個人的な夢はマーケティングにおけるリテールメディアの可能性をトライアルグループに限らず、日本全国に広げることです。2024年の7月からは体制拡大に伴い副社長COOへと立場を変え、引き続き関わらせていただいています。

佐渡島
リテールメディアに対して並々ならぬ想いをお持ちのようですね。
関
電通時代の私は直接広告を作るクリエイターではありませんでしたが、担当した作品が高く評価され、国内外で広告賞を受賞することがありました。広告賞をとるというのは、この業界で働く人間にとって大きな栄誉。ですが、そんな受賞作品が商品の売上や企業の業績に思うようにつながらないことも少なくありませんでした。そういう経験をしているうちに、もっと直接的に売上や業績に貢献することに関わりたいという思いが強くなっていきました。
ちょうどその頃、世の中に少しずつ出始めていたのが、より購買に近いところでお客さまとコンタクトできるリテールメディアでした。トライアルさんもこの領域にすごく注力されており、ご縁があって、一緒に何かできないかという話が持ち上がっていたので、「ぜひやらせてください」と手を挙げさせていただいたというのが経緯になります。
小売の「現場DX」とリテールメディア
佐渡島
さまざまな業界で「現場DX」を実施させていただいている我々の立場から見ても、リテールメディアは非常に可能性のあるものだと感じます。
まず、直接的に売上や業績アップに貢献できる可能性がありますよね。スーパーでお買い物をされる方には、事前に何を買うか決めた上で来店する人もいらっしゃるでしょうが、来店後に商品を見ながら決めるという人も結構多いのではないでしょうか。そうだとすると、店舗内でうまく1to1マーケティングができれば、お客さまの購買行動を大きく変え、利益を向上させられることになります。
そうすると、狙いを持って特定の商品を大量に仕入れることもできるようになりますし、さらにEコマースと連携することなどを通して、利益の構造から変えていくことができるかもしれません。従来のリテール業界は、どうしても営業利益率が3〜7%に収斂する構造にあったと思いますが、その根本解決の糸口になり得るということです。

関
おっしゃる通り、一般的に計画購買と非計画購買の割合は3:7、もしくは2:8と言われています。つまり、お客さまが購入する10個の商品のうち、7、8個はもともとは買うつもりのなかったものなのです。ということは、この8個の商品にどうやって作用していくか、あるいは8個だったものをいかに9個、10個にまで増やしていけるかが重要になります。
その際には、お客さまが「余計なものを買ってしまった」と思うのではなく、「いい買い物ができたな」と思っていただけるような世界でなければなりません。それを作っていけるのがリテールメディアの面白いところだと考えています。
佐渡島
大事な視点です。我々は「三方よし」という考え方を大事にしています。独りよがりなプラットフォームではスケールすることはできないと考え、常にユーザー、会社、世間の三点で思考し、自社利益の追求にとどまらず、みんながWin-Winになれる仕組みを作ろうと努力しています。SalesPlusさんも「小売、メーカー、お客さまのWin-Win-Win」ということを常々おっしゃっていて、そこには共通するものを感じます。
多くの事業者は店舗内でのお客さまの行動からいかに情報を取得するかを考えますが、逆にこちら側から情報を提供することで、お客さま好みの買い物体験を提供できるとも考えられます。例えば、来店前にお客さまが閲覧を行ったウェブの履歴を元に、デジタルカートを通じて、パーソナライズされた商品をレコメンドする、といったことです。
もちろん、プライバシー保護の観点からウェブ履歴などの活用はユーザーの同意が必要ですが、便利になるなら同意される方が多いと思います。それは商品を売りたいメーカーや小売業者にとっても、お客さまにとっても嬉しい結果につながるはずです。
関
トライアルさんも常々「小売業はマッチング業だ」とおっしゃっています。つまり、お客さまの気持ちにマッチするものを勧められれば買ってもらえますし、できなければ他店舗に逃げられてしまう、ということ。ただ、オフラインの店舗はECと違い、店舗面積という制約により、おすすめできる数に限りがあります。それを拡張できる可能性を秘めているのがレジカートだ、というのがトライアルさんのお考えです。

言い換えるならそれは、お客さまのワクワク体験を増幅できる可能性があるということ。私自身もそこに面白さを感じて、一生懸命に取り組んでいるところがあります。
AIによる変革はすでに起きている
佐渡島
改めて小売業の現状の課題をどう見ていらっしゃいますか?
関
先ほど佐渡島社長もおっしゃっていたように、小売業は、産業としての方程式がある程度決まってしまっているところがあります。「敷地面積がこれくらいなら、必要なスタッフの数はこれくらい」「店舗オペレーションにかかるコストを引いていくと、最後に残る利益はこれくらい」というように、すべてが決まってしまうのです。どの小売業者も、どうやってこの「経常利益数%の壁」を超え、高収益産業に変えていけるかに課題感を持っています。
日本全体で人口が減っていく中、小売店舗はオペレーションの人員を維持できなくなりつつあります。ローカルであればあるほど、時給を高くしたとしても人が集まらなくなってきています。言葉を選ばずに言えば、高学歴人材は、いまの小売業で働きたいとは思わない可能性があります。長時間労働に対して、得られる収益があまりに釣り合わない産業だと見ているのです。
そうした彼らの見方はもちろん正しい。しかし、デジタルの力を使えば、全部とは言わずとも、一部それを変えられるのではないかというのが私の期待です。
佐渡島
状況を変えるカギはAIが握っていると思います。これまでは、優秀な人材の定義が記憶力や計算力の高さが頭脳や知能を持つ人という一義的なものでした。しかしながら、最新のAIは計算力や記憶力に関して、人間より圧倒的に知能が高い。でも、最近のAI利用にあたっては、さほど高度なITリテラシーは必要とされません。我々のカメラにもAIが組み込まれていますが、設定は店舗マネージャーが一括して行う、あるいは我々の側で済ませてしまうことができます。現場の皆さんは、予め設定されたAIを簡単に使うことで、これまで一部の人の勘や経験に頼っていた部分を誰もが即時体験、共有できるようになります。

その実例として、北関東を中心に展開する地域密着型スーパー・ベルクさんの取り組みをご紹介したいです。ベルクさんは我々のカメラを使って、お弁当売り場の売上分析を行っています。どういう弁当の置き方をすると粗利が最大化するか、AIカメラを使うことで、勝ちパターンを構造から導き出しているのです。具体的には、売れ筋商品とされてきたカツ丼弁当の近くに、より高単価の商品である松茸弁当をどのように並べると最もお買い上げが増えるかを見出すことに成功しています。
関
興味深いです。
佐渡島
しかも、話はここにとどまりません。従来は売り場担当者の経験と勘に基づき、とにかくカツ丼をたくさん並べていました。その結果、確かにカツ丼はよく売れたのですが、同時に廃棄が増えてしまい、さらにそれを燃やす際に発生する二酸化炭素排出量の増加という問題が起きていたのです。担当者の勘に頼った運営を少し数値に置き換えるだけで、売上+αの問題の解決にもつなげることができています。
関
フードロス、さらにはCO2の問題解決にまでつながってしまうというのは面白いですね。

佐渡島
こうした実例がほかにもいくつかあるのですが、表には出にくいので、世の中には知られていません。リテールメディアが一気に広まったのは、ウォルマートの華々しい成功例が知られたことがきっかけでした。AIを用いた小売の課題解決も、成功事例が共有されれば、一気に普及する可能性がありますね。
関
先ほど「小売業の方程式はすでに固まってしまっている」と話しましたが、お話を聞いているうちに、すごく現場知の豊かな人がデジタルを活用してオペレーションを改善したら、大きく変わり得るのかもしれないと思えてきました。顧客体験としてもよりワクワクするし、なおかつ経常利益も大幅アップするという事例が、近い将来に出てくるかもしれません。
<後編記事はこちら>
著者紹介 About Writer

- 鈴木陸夫
- フリーライター。よりよく生きるとはなにかを学び、実践し、還元したいとの思いで、ジャンルは問わず幅広く取材しています。
この連載について About Serial
「見える」未来を対談する
『見える』が拓く未来について、セーフィーCEO
佐渡島隆平が各界オピニオンリーダーと対話を深めます。
-
01

佐渡島庸平氏(コルク)対談 「世の中によき「目」が浸透すれば、 21世紀の人の生活が、一挙になめらかになるんだね!」
セーフィー代表の佐渡島隆平と、主にコンテンツ制作の世界で活動するエージェンシー「コルク」代表の佐渡島庸平は、名字を同じくするところから察せられる通り、じつは従兄弟同士なんです。同世代であることも手伝って、小さいころからと...
-
02
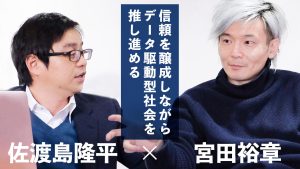
宮田裕章氏対談「日本流のデータ駆動型社会を実現するには『映像データ』がカギとなる」
医療の分野でデータを活用し次世代ヘルスケア改革に取り組む宮田裕章さん。今回は宮田さんの研究所におじゃまし、佐渡島と宮田さんそれぞれが描く「データ駆動型社会」を語ります。 宮田裕章さん2003年3月東京大学大学院医学系研究...
-
03
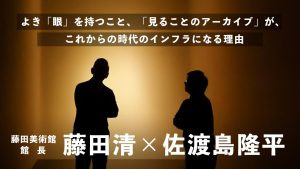
藤田清氏(藤田美術館館長)対談 「 よき『眼』を持つこと、『見ることのアーカイブ』が、 これからの時代のインフラになる理由」
収蔵品数は国宝9件と重要文化財53件を含むおよそ約2,000件。大阪にある藤田美術館は、古くからその名を広く轟かせています。現在はリニューアル期に入っている館に、藤田清館長を訪ねました。セーフィー代表・佐渡島と藤田館長に...
-
04

キヤノンMJ足立正親氏対談「映像が切り拓く未来へ、思いと人間力が紡いだ8年間の共創の軌跡」:前編
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)とセーフィー株式会社(以下、セーフィー)の関係は2017年の資本業務提携からスタートし、その後も映像データの利活用を軸に、さまざまな形でパートナーシップを深めて...
-
05

キヤノンMJ足立正親氏対談「両者が見据える「想像を超えた未来」。社会課題解決に映像はどう寄与できるか」:後編
前編に引き続き、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)代表取締役社長・足立正親さんとセーフィー株式会社代表取締役社長CEO・佐渡島による対談をお届けします。後編では、両者が映像データ活用で見据える「...
-
07

SalesPlus関晋弥氏対談「未来の小売店舗、三方よしの顧客体験」:後編
前編に引き続き、株式会社SalesPlusの関晋弥代表取締役副社長COOと、セーフィー代表取締役社長CEOの佐渡島による対談をお届けします。小売業界が直面する課題と、デジタルが持つ変革の可能性を概観した前編、後編では小売...