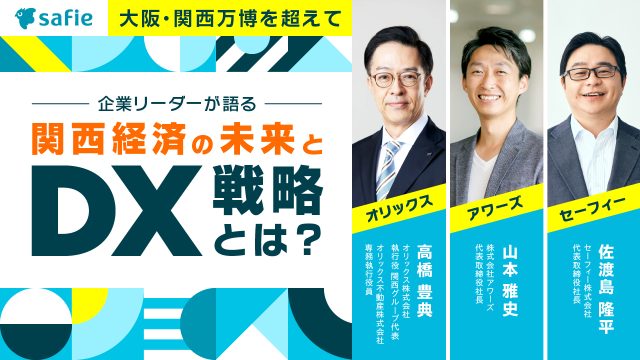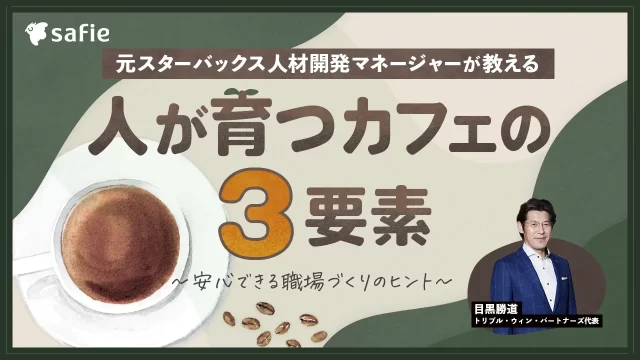工事の進捗を確認するために、実際に現場へ足を運ぶ責任者は珍しくありません。しかし、スケジュールの都合をはじめ、諸事情で現場へ赴く時間が確保できないケースもあるでしょう。その場合は、ウェアラブルカメラによる遠隔臨場がおすすめです。
本記事では、遠隔臨場におけるウェアラブルカメラのメリットについて解説します。また、ウェアラブルカメラで遠隔臨場をする方法や実際の事例もまとめてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
そもそも遠隔臨場とは?
遠隔臨場とは、離れた場所から臨場、つまり工事現場の立ち会いを行うことです。国土交通省では材料確認や段階確認、立会を遠隔で実施することと定義されています。(※1)
遠隔臨場が建設業界で実施されるようになった背景、そして遠隔臨場を実現する技術とその仕組みに関する解説は、以下のとおりです。
建設業界で遠隔臨場が行われるようになった背景
建設業界で遠隔臨場が広まった背景として、ICT化の推進や新型コロナウイルスのパンデミックなどが挙げられます。また、少子高齢化を起因とする労働者の人手不足の負担を軽減する方法としても、遠隔臨場が行われるようになりました。
遠隔臨場を実現する技術・仕組み
遠隔臨場は、主にウェアラブルカメラやネットワークカメラを用いて実施されます。ウェアラブルカメラの装着やネットワークカメラの設置は、現場作業員が行うのが一般的です。撮影した映像はシステムを通じて遠隔地にある本部や支部に届けられます。
これにより、責任者や監督者は離れた場所からリアルタイムで現場の状況を確認することが可能です。
遠隔臨場を行うことで、発注者・受注者双方にはそれぞれ次のようなメリットがあります。
遠隔臨場やウェアラブルカメラのメリット
遠隔臨場やウェアラブルカメラの導入にはさまざま背景がありますが、それだけではなくメリットも存在しています。具体的な遠隔臨場やウェアラブルカメラのメリットは、以下のとおりです。
現場業務の効率化
主なメリットの1つとして、現場業務の効率化が挙げられます。従来の臨場の場合、責任者が諸般の事情で現場に足を運べず、確認作業が滞り工事のスケジュールに遅れが発生することも珍しくありませんでした。
しかし、遠隔臨場やウェアラブルカメラが登場したおかげで、現在では現場に行かずにリモートで確認作業が可能になっています。
移動やスケジュール調整の手間や移動費の削減
スケジュール調整の手間や、移動費の削減ができる点もメリットです。工事現場への移動時間や移動手段を確保するのは、決して楽なことではありません。
とくに複数の現場を抱えている場合、スケジュールの調整はもとより、責任者自身への負担が大きくなりがちです。遠隔臨場やウェアラブルカメラを導入すれば、大幅な作業時間短縮の実現のほか、移動時間や待機時間の削減、無駄なコストカットなどができます。
撮影中の両手の自由
撮影中に両手の自由を確保できるのも、ウェアラブルカメラを採用するメリットです。どれだけ本体のサイズが小さくても、カメラを操作するために必ず片手は必要でした。
ウェアラブルカメラなら、撮影中でも両手の自由を確保できるため、撮影と作業の同時進行ができます。また、閲覧側の管理者も臨場感のある映像をチェックすることで、リアルタイムでの現状把握が可能です。
社員教育・技術の継承
社員教育、そして技術の継承の際にも活躍が見込めます。たとえば、若手社員がウェアラブルカメラを装着した状態で作業すれば、その様子を遠隔地にいるベテラン従業員が確認し、都度アドバイスできるため、若手社員の早期育成が期待できるでしょう。
また、撮影した映像を残せば、1年に数回しか行われない作業や工事の様子や手順をほかの従業員に教えられます。
安全管理の効率化
ウェアラブルカメラは過去の記録を参照することで、事故の原因を追究し、再発防止策を講じるためのデータを収集できます。また、現場監督や安全管理者が遠隔地にいてもリアルタイムで現場の状況をチェックできるため、即座の指示や指導によって、作業中の安全性を劇的に向上させることが可能です。
遠隔臨場やウェアラブルカメラの課題・注意点
遠隔臨場やウェアラブルカメラは、さまざまなメリットをもたらしてくれる存在ですが、いくつか押さえておきたい課題や注意点も存在します。具体的な課題、および注意点は、以下のとおりです。
導入費用が高くなることがある
遠隔臨場やウェアラブルカメラの課題として、導入費用の高さが挙げられます。遠隔臨場を実施するためには、ウェアラブルカメラや録音機器など、さまざまな機材を用意しなければなりません。
高機能なカメラの導入や、大量のカメラを設置する場合は、負担が大きくなる可能性があります。
通信環境の整備・確保が必要になる
遠隔臨場は、オンライン上で映像と音声を双方向でやりとりします。そのため、ネットワーク環境が悪いと、スムーズにコミュニケーションが取れず、作業の安全性にも影響が出かねません。
作業を滞りなく進行させるためにも、通信環境の整備、および確保は重要な課題です。
IT機器に不慣れな技術者への対応・配慮が必要になる
IT機器の知識や経験が浅い従業員への対応、および配慮も、遠隔臨場における課題の1つとして挙げられます。遠隔臨場を実施する際、専門性が高く扱いが難しい機材を使用する機会は、そこまで多くありません。
しかし、従業員がIoTデバイスの操作に慣れず、ミスやトラブルが発生する可能性があります。そのため、マニュアルの整備やサポートサービスの導入、研修の実施などを通じて従業員の練度を高めなければなりません。
プライバシーへの配慮が必要になる
ウェアラブルカメラを使用するにあたって、プライバシーへの配慮も考える必要があります。現場の状況を映像として記録する際、現場の従業員をはじめとするその場にいる人物が映り込んでしまいがちです。
もし録画した映像を研究や研修の資料として無断使用した場合、カメラの映像に映っている個人のプライバシーを侵害していると判断される可能性があります。
ウェアラブルカメラで遠隔臨場を行う方法
ウェアラブルカメラで遠隔臨場を行う方法について解説します。受注者側と発注者側で操作の詳細が異なるため、順番にチェックしていきましょう。
実施の流れ(受注者側)
受注者側は、ウェアラブルカメラを身につけて現場の様子を撮影しながら説明が可能です。ウェアラブルカメラを装着する場所として、ヘルメットやネックマウント、シャツの胸ポケットなどが挙げられます。
また、カメラ本体を手に持ち替えれば、対象物を鮮明に撮影することも可能です。
実施の流れ(発注者側)
発注者側は、ウェアラブルカメラが撮影した現地の映像を、リアルタイムで確認可能です。映像を視聴するにあたって、専用のアプリをダウンロードする必要はとくにありません。通話機能が搭載されているウェアラブルカメラであれば、受注者側が撮影した映像の確認と会話を同時にこなせます。
遠隔臨場向けウェアラブルカメラ「Safie Pocket シリーズ」

遠隔臨場用のウェアラブルカメラとしては、多くのゼネコン企業での導入実績をほこるウェアラブルクラウドカメラ「Safie Pocket(セーフィー ポケット)シリーズ」がおすすめです。
| モデル | 画像 | 特長 | 防水防塵 |
|---|---|---|---|
| Safie Pocket2 |  | シンプルな機能構成のエントリーモデル | IP67 |
| Safie Pocket2 Plus |  | 遠隔業務に必要な機能をフルパッケージ | IP67 |
LTE通信機能搭載、ネットワークの設定が完了した状態で手元に届くため、煩雑な初期設定を行う必要がありません。また、操作もシンプルで、電源を入れて、カバーを降ろすだけで録画を開始できます。
Safie Pocketシリーズで遠隔臨場を行うメリット
リモートで工事現場をチェックできるカメラは複数存在しますが、Safie Pocketシリーズにはほかの機種にはない独自の強みがあります。以下では受注者側と発注者側、それぞれの視点からSafie Pocketシリーズのメリットについて解説します。
メリット(受注者側)
受注者側の主なメリットは、次の3点です。
- 背面ディスプレイ付き
- 人間の視野とほぼ同じ画角で撮影ができる
- 長時間の使用が可能
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
ポイント1. 背面ディスプレイ付き
Safie Pocketシリーズは、背面ディスプレイが搭載されたウェアラブルカメラです。そのため、撮影中はプレビュー表示で確認しながら映像を記録できます。
また、ディスプレイではネットワークの接続状態のチェック、設定をはじめとするメニュー操作も可能です。
ポイント2. 人間の視野とほぼ同じ画角で撮影ができる
Safie Pocketシリーズの強みとして、画角の広さも挙げられます。一般的なウェアラブルカメラやスマホは画角、つまりカメラに対象が映る範囲が広いとはいえません。そのため、撮影対象を上手く記録できないことも多いです。
しかし、Safie Pocketシリーズの画角は人間の有効視界とほとんど同じ約120度のため、撮り逃しの発生を抑える効果が期待できます。
ポイント3. 長時間の使用が可能
長時間の使用が可能な点も、Safie Pocketシリーズのメリットです。バッテリー稼働時間は最大8時間のため、三脚とセットで使用すれば、1日の作業の様子を最初から最後まで記録できます。
メリット(発注者側)
発注者側のメリットとして、次の3点が挙げられます。
- カメラにタグを設定できる
- 映像の振り返りが簡単
- 報告書作成の負担軽減
それぞれのメリットの詳しい解説は、以下のとおりです。
ポイント1. カメラにタグを設定できる
Safie Pockeシリーズには、タグ設定機能が搭載されています。複数のカメラを管理する際に便利で、それぞれのカメラのグループ分けも簡単です。当日使用するカメラに、日付と時間を設定しておくとよいでしょう。
ポイント2. 映像の振り返りが簡単

タイムライン上で確認したい時間を左右にドラッグするだけで、映像の振り返りも簡単に行える点もメリットです。倍速再生機能も搭載されており、早送りしながら気になった部分の映像のみ確認できるため、作業効率の向上も期待できます。
ポイント3. 報告書作成の負担軽減
作業報告書の負担を軽減できる点も、メリットとして挙げられます。1日の作業をまとめるのは煩雑で、都度何が起きたのか思い出すのも簡単ではありません。
しかし、Safie Pocketシリーズであれば、映像記録から必要な情報をピンポイントで調べられます。また、ダウンロードした動画を電子報告書に載せることも可能です。
Safie Pocketシリーズを活用した遠隔臨場の事例
最後に、Safie Pocketシリーズを活用した受注者側と発注者側、それぞれの遠隔臨場の事例を取り上げます。遠隔臨場の採用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
受注者側
まずは、受注者側の事例として、以下の2つを紹介します。
- 株式会社大林組 さま
- 若築建設株式会社 さま
遠隔臨場によってどのように現場が変わったのか、順番にチェックしていきましょう。
株式会社大林組 さま
創業1892年の歴史を誇る大手ゼネコン、株式会社大林組でも遠隔臨場が導入されました。その結果、移動コスト削減やベテラン技術者の業務効率化に成功し、残した映像も技術伝承や研修などに有効活用されています。
若築建設株式会社 さま
海洋土木業界に携わっている若築建設株式会社は、かつて100を超える現場を毎月視察していました。しかし、コロナの影響で現地視察が難しくなったことで遠隔臨場を導入し、現地視察の大幅な効率化に成功しています。
発注者側
発注者側は、東日本高速道路株式会社さまの事例を取り上げます。Safie Pocketシリーズの導入による具体的な労働環境の変化は、以下のとおりです。
東日本高速道路株式会社 さま
東日本高速道路株式会社では、道路工事の遠隔臨場にSafie Pocketシリーズを採用しました。その結果、現地立会と比較して移動時間を6割軽減し、映像による情報共有によって検討事項の判断も早まり、現場でのタイムロスの削減にも成功しています。

ウェアラブルカメラで遠隔臨場や業務効率化を図ろう
労働人口の減少が進む昨今、業務効率の向上は建設業界をはじめ、各業界が取り組まなければならない課題です。ウェアラブルカメラによって遠隔臨場を実施すれば、業務の効率化はもちろん、さまざまなメリットが得られます。
Safie Pocketシリーズは、LTE搭載のためカメラ単体で遠隔臨場のための撮影・録画が可能なクラウド型のウェアラブルカメラです。導入実績も多数あり、円滑な現場導入を可能にするノウハウ・経験も多くありますので、ぜひお問い合わせください。
- 「Safie Pocket」シリーズ紹介
- ウェアラブルクラウドカメラでの遠隔業務をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
出典:”建設現場における遠隔臨場に関する実施要領”.国土交通省.2024-3(参照2024-10-23)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。