
Writer:鈴木陸夫
2025/08/28
キヤノンMJ足立正親氏対談「両者が見据える「想像を超えた未来」。社会課題解決に映像はどう寄与できるか」:後編
前編に引き続き、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)代表取締役社長・足立正親さんとセーフィー株式会社代表取締役社長CEO・佐渡島による対談をお届けします。後編では、両者が映像データ活用で見据える「想像を超えた未来」とはどのようなものなのか、また、きたる「8がけ社会」に代表される社会課題の解決やDXに、映像がもたらし得る新たな価値を語り合いました。
<前編記事はこちら>

カギを握るのは顧客起点のイノベーション
佐渡島
日本では少子高齢化が進み、2040年頃には現役世代(15〜64歳)の人口が現在の8割に減少すると予測されています。いわゆる「8がけ社会」の到来です。「8がけ社会」においては、当然のことながら、一人当たりのやるべきジョブが多くなります。そこに向けて、生産性向上が喫緊の課題になっています。
その解決に貢献していくためには、お互いの本業をかけ合わせ、今以上に加速してシナジーを作っていくことが大事になると思っています。中でもわれわれが注目しているのは、キヤノンMJさんの未来志向で新規事業を創出する「Research & Business Development」(以下、R&B)の取り組みです。足立社長が常々おっしゃっていることですが、お客さまを起点に、社内・社会双方のイノベーションを実現されていますよね。
唐突ですが、このことについて話すのに、私はよくドラえもんの話をします。ドラえもんは四次元ポケットから「どこでもドア」も出すけれど、「タケコプター」や「通りぬけフープ」も出すじゃないですか。遠くへ行くという目的からロジックで考えたら「どこでもドア」さえあればいいはずなのに、いろいろな道具があるのはなぜなのか。それはその人、その時々のユーザーニーズがあるからですよね。「タケコプター」が必要なのは「しずかちゃんと一緒に飛んでいきたい」というのび太くんのWantsがあるからでしょう。

一般消費者は、「どこでもドア」を開けたら即座に目的地に着くような世界を望んでいないのだと思います。目の前の困りごとを解決してくれるプロダクトやサービスを求めている。そのニーズを起点に考えると、ソリューションはある意味、無限に生み出せます。その視点をわれわれとしてもすごく大事にしています。キヤノンMJさんとも、ご一緒に顧客起点でビジネスをつくれると、非常に面白いと感じています。
足立
われわれの「R&B」は、5年先、10年先の社会課題を見据え、おっしゃるように顧客起点で新しいビジネスモデルを作る取り組みです。その解決の糸口は必ずしも映像ソリューションばかりではないかもしれませんが、ゆくゆくは必ず「映像を使った方が解決の精度が上がる」「高度になる」という話になると思っています。
労働人口の減少はもちろんですが、近年では自然災害も増え甚大化しています。そうした課題解決には「目」となるセンサーが重要な役割を果たすことは間違いないと思います。映像ソリューションによる解決の幅を広げていくためにも、今後ますます協業を活性化させていかないといけないと考えています。
多様化・複雑化する社会課題解決のためには、セーフィーさんとうちの技術・ノウハウだけでは足りないでしょう。先日共同出資を発表したMODE社のように、AIスタートアップとの提携も引き続き進める必要があります。その「輪を広げる」ところも御社に期待しているところです。

佐渡島
日本の「8がけ社会」は、世界から見たら課題先進国としての姿です。ですから私としては、つくった価値を輸出していきたいとも思っています。キヤノングループのお力もお借りしてグローバルに展開できると、日本の社会課題解決そのものが、日本の国力を増すことにつながっていくでしょう。国内でとどまっている従来のDXには、単なるデジタルへの置き換えで終わってしまっているものも少なくないかもしれません。そこからさらに「稼ぐ」というところまでいけるとユニークですし、可能性は広がります。そういう方向で協業をさらに深めていきたいですね。
社会的合意を得るための終わりなき哲学的議論
佐渡島
映像データによるイノベーションを進める上では、社会のコンセンサスをいかにつくるかも大事になります。個人情報保護法やIoTのカメラ活用ガイドブックなど、国によるルールメイキングが進んでいますが、この領域は必ずしも法律でキッパリと線引きをし、罰則を決めれば済む話ではありません。
映像データの中にはあらゆる個人情報が含まれています。会話の内容、服装、さらにはその人の心情まで、あらゆることが入ってしまっていますよね。そのデータをAIが活用して、ということになると、どうしても気持ち悪さの問題にぶつかります。倫理観そのものが問われてくることが非常に大きなポイントです。
そこでわれわれは「データガバナンス委員会」というものを設け、どうすれば「三方よし」の状態をつくって進められるのか、プライバシーや消費者保護などの観点からプラットフォームの在り方について継続的に議論しています。そこには憲法学者、弁護士といった専門家の方々に加えて、もちろんキヤノンMJさんにも入っていただいています。
先ほど足立社長からお話のあった「アンテナ感度」のようなところが、実は一番大事だと感じています。「こういう使い方・見せ方・やり方をしたら、消費者から見たら気持ち悪いよな」「法律には違反していないけれど、守っていかなければならないよな」。そのように自ら襟を正していく姿勢が大事になるのではないでしょうか。
足立
セキュリティやプライバシーの問題は昔から言われてきたことです。例えば介護施設などでは、人物にシェードをかけてご家族にだけ見られるようにするなど、われわれもいろいろと試行錯誤してきました。ただ、「共同スペースにカメラがあるのはいいが、そもそも個室には置きたくない」という声もあります。この辺りの問題に対してブレイクスルーを起こしたいと考えますが、いかがでしょうか?
佐渡島
介護の現場に関するガバナンス委員会での議論を少し紹介させてもらうと、介護施設には、職員が気が付かない間に倒れられているかもしれない、お亡くなりになっているかもしれないというリスクに対応する安心安全対策の話もあるのですが、同時に人間の尊厳の問題があります。意識のある方なら「着替えている姿は見られたくない」「排泄しているところは嫌だ」と主張できますが、老化や病気の進行により、自意識の中で認知ができない状態になった方だと、そうはいきません。
そういう人の尊厳について、どう考えるのか。それは本人の尊厳の問題でもあるし、家族の尊厳の問題でもあります。さらにはその業界、社会の尊厳の問題にまで広がっていく。その同意をどのようにしていただくのか、というのは非常に大事な論点になります。これは簡単には答えを出せない問いです。
類似の事例として、臓器提供の意思表示の話を参照すると、日本の免許証の裏側には、目や胃や脳などの臓器を「提供しますか?」と書いてあり、マルをしたものだけがその人の死後に提供されます。要するに、オプトイン方式です。一方、フランスなどではオプトアウト方式が取られています。その結果、9割の人が「提供する」という意思表示をしているのがヨーロッパの社会です。
このように、社会の反応というのは、前提をどちらに揃えるかによってもまったく違う結果として現れます。何が正しいのかという議論は、それくらいに一様には決められないもの。必然的に、議論は哲学的な内容になっていきます。

足立
国によって風土風習も異なるから、簡単ではないですよね。
佐渡島
そんな中、この問題をどうにか解決している例もあります。紹介したいのは、グーグルの「ストリートビュー」の事例です。ストリートビューは、街中のあらゆる景色を丸見えにしました。そこには家、車、人も映っている。一方で、車のナンバープレートや表札、人の顔はぼかし処理をしました。その結果、ここまで技術的なカバーをすれば、そのサービスは有益なものであるという解釈がなされた。社会の景色はプライバシーではないという線引きがなされたわけです。
このようにテクノロジーとプライバシーは非常に密接な関係があります。テクノロジー企業の社会的役割として、こうした問題もテクノロジーで解決していくという視点は非常に大事なポイントかと思います。
足立
国によって温度差はありますし、尊厳の問題は難しい領域でもあるため慎重に進める必要がありますが、人口減少などの問題もあり、継続的にしっかりと向き合っていかなければなりませんね。
映像×AIがもたらす「想像を超えた未来」
足立
私は、希望ある、幸せな社会を作っていきたい。社員にもことあるごとにそういう話をしています。では、希望のある社会とはどのような社会でしょうか。一つは安心安全な社会、そして、意欲さえあれば誰もが学べる、成長できる世の中である必要があると思っています。
そのような社会を実現していくために、映像ソリューションがもたらす価値は大きいと考えています。
佐渡島
われわれの「映像から未来をつくる」というビジョンには、人の意思決定をスマートにしていくことが含まれています。別の言い方をするなら、それは「一歩前を知る」ということです。たとえば、ここで火事が起きたとします。火災報知器や映像により素早くそれを検知できたら、大事になる前に消すという意思決定ができますよね。このように人の意思決定の一歩前を知ることができると、安心安全な社会につながっていきます。
さらに、ここにAIが加わると、ことが起きる前に対処するということも可能になります。人が保険に入るのは何か起きたときのためですが、同時に何も起きないことを願って入るわけです。それは現時点では「神頼み」のようなものですが、技術やサービスにより、本当に何も起きない世界を実現することができたら、それはおそらく足立社長のおっしゃる安心安全な社会と言えるのではないでしょうか。
「一歩前を知る」ことに加えて、フィードバックし続けることも重要です。たとえば、ドライブレコーダーで運転を常に記録し、フィードバックし続けることで、安全な運転に近づけることができます。UberやGrabのようなサービスもそうです。運転者へのフィードバックシステムを入れたことにより、不正な請求が減り、運転手と利用者の双方に快適な社会に近づきました。AIでフィードバックしていく社会というのは、衣食礼節の礼節をテクノロジーが実現する社会です。映像やデータでうまくイノベーションを起こすことができれば、そんな社会を作っていけると想像しています。

足立
それにはやはり映像データだけではだめだということですよね。それ以外のデータと組み合わせ、さらにそのデータに基づいてAIが判断するということですから。
佐渡島
その通りだと思います。とある飲食店グループのデータ分析基盤に弊社のカメラを使っていただいているのですが、そこでは非常に面白い取り組みがなされています。「従業員の方が何歩くらい歩くと離職率がこれくらい上がる」「お客さまがどれくらいの滞在時間で満足して帰っていらっしゃるのか」「片づけられていないテーブルを片づけて水を出すだけで利益が最大化する」など、映像と周辺のデータを組み合わせることによって見えなかった価値を見える化し、そのデータをM&Aなどの意思決定に活用しているのです。
「お客さまが並んでいるのにテーブルが片付けられていない」といったことは、仕方なく起きていることです。注文を取らないといけない、提供しないといけないという目の前の仕事に追われているから、人間の第一、第二の目では、お客さまが列を作っている姿は確認できません。そこにカメラという第三、第四の目があることで、映像データを元に「先にお客さまを案内して」といった指示ができるようになります。逆にまったく並んでおらず、店内も空いているのであれば、SNSに情報をアップして集客することもできるわけです。
足立
チェーン店なら「この店舗は空いていないけれども、同じグループの別の店なら空いている」と案内することもできますね。
佐渡島
おっしゃる通りです。デジタルに置き換えることで人手不足の問題を解決しているようでいて、実は集客にもつながっている。そういう取り組みをするベンチャー企業なども出てきています。他にも、お客さま一人一人が持っている映像データから、よりきめ細かい天気予報が実現するかもしれない、などアイデアは尽きません。このようにさまざまな角度からデータを活用するサービスが生まれてくると、ビジネスとしても面白くなっていきますよね。
足立
それこそが真のDXですよ。DXというのは単にデジタル化することではなく、ビジネスモデルを変えること。コストダウンというよりは、分かりやすくいうと「いかに企業変革を実現し、利益を生み出すことができるか」という話です。そういうことにつながっていくといい。
佐渡島
御社の社員の方にいつもご質問いただくのもそこです。「それをやって、お客さまのビジネスに利益が出るんですか?」と。とても大事なポイントだと思います。お客さまの利益に貢献するという話もしないと、Win-Winにはなれない。われわれとしてもそういう探索を常にしながら、未来をつくっていきたいです。
足立
やっぱりお客さまも利益につながらないことには投資をしませんからね。社会に広く受け入れられるには、安心安全は大変重要ですが、付加価値がなければダメだということでしょう。

佐渡島
足立社長が常におっしゃっている、顧客起点の変革が求められているのだと改めて感じます。お客さまが抱える問題や課題をお客さまと一緒になって深く見て、チャンスを見つけ、大きくしていく。DXやIoTビジネスというのはその繰り返しなのだろう、と。ですから、できる限りお客さま視点に立ち、繰り返し探索し、解決し、またそれを再投資してより大きなビジネスに変えていく。そこをぜひご一緒していきたいです。
足立
これまでの8年の歩みにより、一緒になって新たなものを作っていける信頼関係をしっかりと築くことができたと思っています。今後ともぜひよろしくお願いします。
著者紹介 About Writer

- 鈴木陸夫
- フリーライター。よりよく生きるとはなにかを学び、実践し、還元したいとの思いで、ジャンルは問わず幅広く取材しています。
この連載について About Serial
「見える」未来を対談する
『見える』が拓く未来について、セーフィーCEO
佐渡島隆平が各界オピニオンリーダーと対話を深めます。
-
01

佐渡島庸平氏(コルク)対談 「世の中によき「目」が浸透すれば、 21世紀の人の生活が、一挙になめらかになるんだね!」
セーフィー代表の佐渡島隆平と、主にコンテンツ制作の世界で活動するエージェンシー「コルク」代表の佐渡島庸平は、名字を同じくするところから察せられる通り、じつは従兄弟同士なんです。同世代であることも手伝って、小さいころからと...
-
02
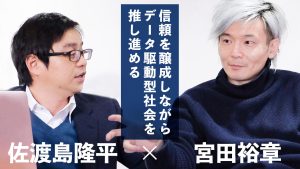
宮田裕章氏対談「日本流のデータ駆動型社会を実現するには『映像データ』がカギとなる」
医療の分野でデータを活用し次世代ヘルスケア改革に取り組む宮田裕章さん。今回は宮田さんの研究所におじゃまし、佐渡島と宮田さんそれぞれが描く「データ駆動型社会」を語ります。 宮田裕章さん2003年3月東京大学大学院医学系研究...
-
03
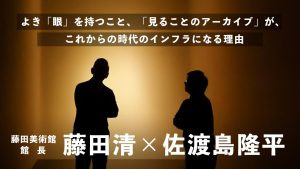
藤田清氏(藤田美術館館長)対談 「 よき『眼』を持つこと、『見ることのアーカイブ』が、 これからの時代のインフラになる理由」
収蔵品数は国宝9件と重要文化財53件を含むおよそ約2,000件。大阪にある藤田美術館は、古くからその名を広く轟かせています。現在はリニューアル期に入っている館に、藤田清館長を訪ねました。セーフィー代表・佐渡島と藤田館長に...
-
04

キヤノンMJ足立正親氏対談「映像が切り拓く未来へ、思いと人間力が紡いだ8年間の共創の軌跡」:前編
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)とセーフィー株式会社(以下、セーフィー)の関係は2017年の資本業務提携からスタートし、その後も映像データの利活用を軸に、さまざまな形でパートナーシップを深めて...
-
06

SalesPlus関晋弥氏対談「リテールメディアは小売の課題を解決できるか」:前編
九州に本社を置く小売企業トライアルホールディングス(以下、トライアル)は、業界の変革を目指し、お客さまの快適なお買い物体験につながるデジタルサイネージやレジカートなどのリテールメディア、さらには安心安全な店舗運営にむけて...
-
07

SalesPlus関晋弥氏対談「未来の小売店舗、三方よしの顧客体験」:後編
前編に引き続き、株式会社SalesPlusの関晋弥代表取締役副社長COOと、セーフィー代表取締役社長CEOの佐渡島による対談をお届けします。小売業界が直面する課題と、デジタルが持つ変革の可能性を概観した前編、後編では小売...