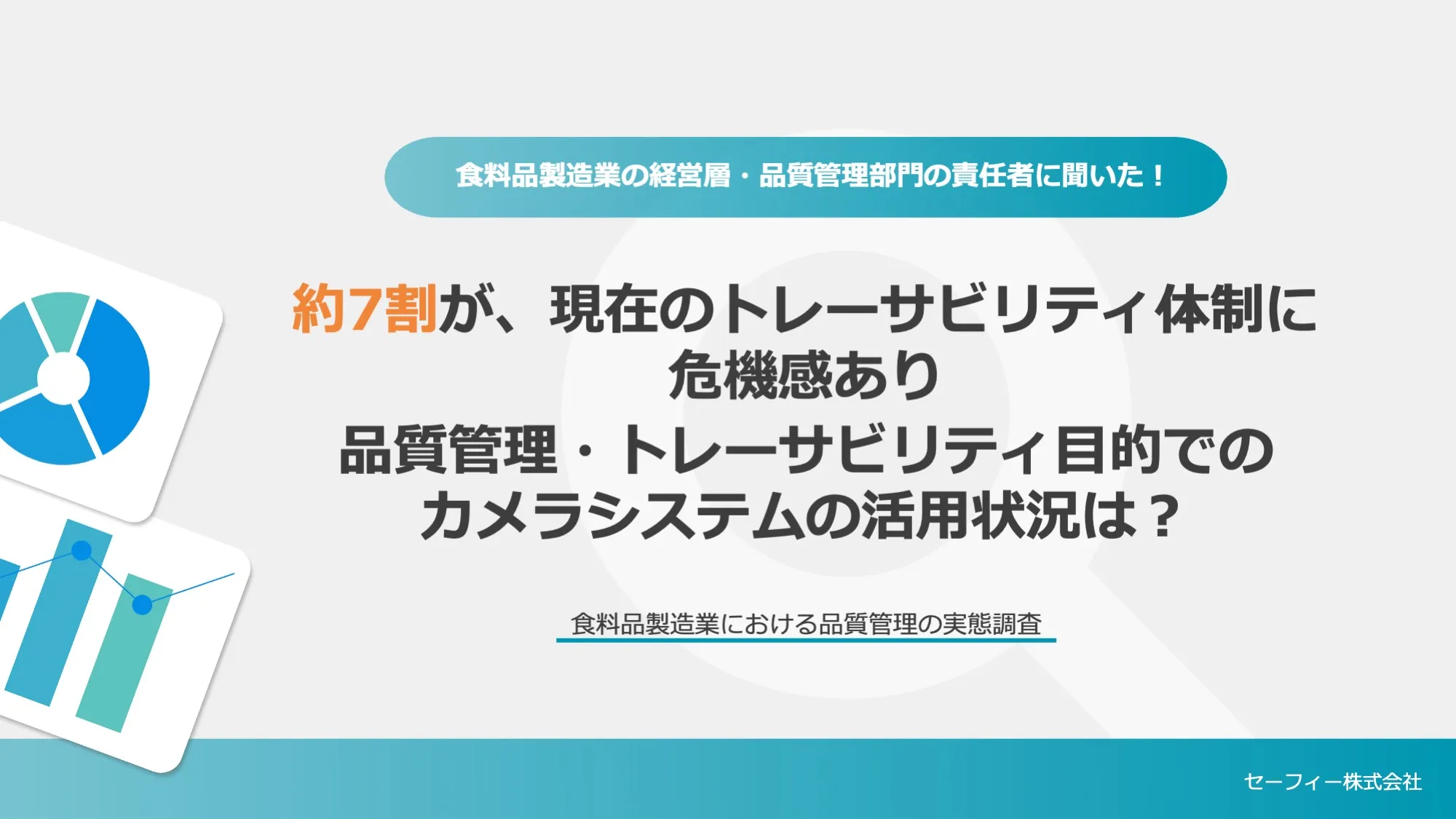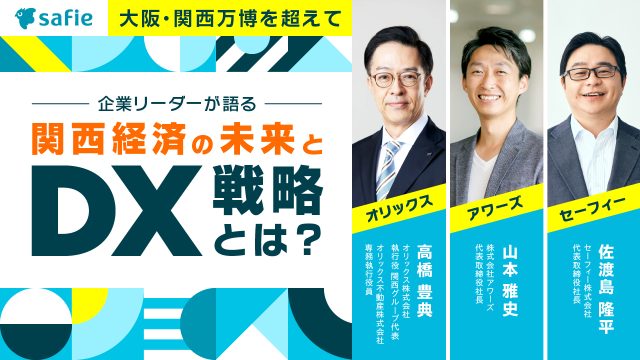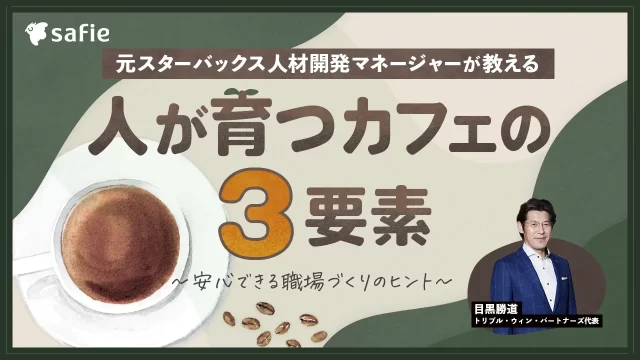食品トレーサビリティシステムの導入に踏み切れず、「コストに見合うのか」「現場が混乱しないか」「どんなシステムを選ぶべきか」と悩んでいませんか?
食品トレーサビリティシステムは、適切に導入することで、企業担当者が抱える不安を解消し、紙やExcelの管理から効率的なシステム管理への移行を実現できます。
この記事では、食品トレーサビリティシステム導入の法的背景やメリット、現場への浸透方法、製造〜出荷までの管理フローからシステム選定のポイントまで、実践的な知識を解説します。
目次
食品トレーサビリティシステムとは

食品トレーサビリティとは、食品が生産から消費されるまでの段階すべてを追跡できる仕組みのことです。食品の安全性を担保するうえで重要であり、業界で近年注目されています。
食品トレーサビリティシステムは、主に以下の手順で運用されます。
- 原材料の入荷記録を付ける
- 食品を加工・製造したときの記録をつける
- 加工・製造した食品の出荷記録を残す
これは各段階をバーコード、二次元コード、RFIDなどで読み取り、システムに登録することで、問題が発生した段階を確認しやすくする仕組みです。
まずは食品トレーサビリティシステムを導入する前に、基礎的な知識や、トレーサビリティがなぜ求められているのかを知る必要があります。
また、トレーサビリティには内部トレーサビリティとチェーントレーサビリティの2つのタイプが存在します(後ほど解説します)。違いを理解し、自社にはどちらが適しているかを確認しましょう。
食品業界でトレーサビリティが求められる理由
食品業界でトレーサビリティシステムが求められる背景には、食の安全・安心への意識の高まりがあります。特にBSE(牛海綿状脳症)問題や食品偽装事件などの発生により、行政による法規制が強化され、牛トレーサビリティ法や米トレーサビリティ法の制定、食品衛生法の改正によるHACCP義務化などの制度が整備されてきました(※1、※2)。
企業側にとっても、万が一の食品事故発生時に原因究明と対象範囲の特定を迅速に行うことで、被害拡大を防止し、ブランドイメージを保護する重要な手段となっています。現在では企業のリスク管理体制を明確にし、製品の品質や安全性を保証する重要な指標へとその位置づけが変化しています。
消費者からの信頼獲得と競争力強化のためにも、単なる法令遵守を超えた積極的な情報開示と透明性の確保が求められる時代となっているのです。
追跡できる範囲と仕組み
食品トレーサビリティシステムは、「どこで」「誰が」「いつ」「どのように」「何を使って」製造・流通させたかという情報を記録・管理する仕組みです。
食品トレーサビリティシステムの記録管理では、原材料の入荷から製品の出荷までのデータを、追跡(トレースフォワード)と遡及(トレースバック)の両方向で把握できます。記録するタイミングと記録内容は、主に以下の通りです。
| 記録タイミング | 記録内容 |
| 原材料入荷時 | ロット番号、産地、製造元情報 |
| 製造工程 | 使用原料、製造設備、作業者、製造日時、品質検査結果 |
| 出荷時 | 製造ロット番号、出荷先、出荷日時 |
上記の内容を記録することで、問題発生時に原因の特定や影響範囲が把握できます。情報管理には、バーコード、二次元コード、RFIDなどの識別技術と専用ソフトウェアを組み合わせて活用します。
QRコードは消費者がスマートフォンで簡単に読み取れるため、製品パッケージに印刷して産地情報などを提供する用途にも活用が可能です。効果的なトレーサビリティの実現には、各工程における正確なデータ記録と、それらを連携させる仕組みが不可欠なのです。
内部トレーサビリティとチェーントレーサビリティの違い
トレーサビリティは内部トレーサビリティとチェーントレーサビリティの2つのタイプに分けられます。
内部トレーサビリティは、自社工場内での原材料の入荷から製品の出荷までの工程における製品や原材料の流れを把握するものです。食品メーカーでは、工場内での計量ミス・誤投入防止と製造ロットを管理し、トレース時間の短縮に活用されています。
一方、チェーントレーサビリティは、原材料の生産者から消費者に至るまでのサプライチェーン全体を通じた製品の移動を把握するものです。例としては生産農家から畜場、食肉処理、卸売、小売までの一貫した個体識別番号による管理が行われている牛肉トレーサビリティが挙げられます。
内部トレーサビリティは自社のみで商品の移動、加工品質検査の履歴を確認でき、問題発生時の迅速な原因特定が可能なため、着手しやすいのがメリットです。一方、チェーントレーサビリティはサプライチェーン全体の協力が必要であり、実現には大きな調整が求められるものの、消費者への透明性向上やブランド価値向上などの付加価値を生み出します。
どちらのトレーサビリティを導入するかは自社の状況に応じて検討し、段階的に取り組むことを頭に入れておきましょう。
食品トレーサビリティシステム導入のメリット
食品トレーサビリティシステム導入によって得られる具体的なメリットは、次の4つが挙げられます。
- 問題発生時に迅速な対応ができる
- 消費者からの信頼向上に貢献できる
- 食品ロス削減に寄与できる
- 企業ブランド価値が上がる
それぞれ見ていきましょう。
問題発生時に迅速な対応ができる
食品トレーサビリティシステムの重要なメリットは、食品事故や品質トラブルが発生した際の迅速かつ正確な対応力です。システム導入により、製品の製造履歴や流通経路が詳細に記録されるため、問題発生時に「いつ」「どこで」「どの原材料」「どの工程」で問題が生じたのかを速やかに特定できます。
また、どの製品ロットに影響があるかを正確に把握できるため、必要最小限の範囲での回収が可能になり、過剰な回収による経済的損失を防ぎます。
製品回収のスピードと正確性向上は、消費者の健康被害の拡大防止だけでなく、問題の迅速な解決による企業信頼回復にもつながります。複雑な原材料や製造工程がある食品製造業では、リスク管理の強化が実現でき、大きな価値があるのです。
消費者からの信頼向上に貢献できる
食品トレーサビリティシステムは、製品の産地、原材料、製造工程などの情報を高い透明性をもって消費者に提供することで、食の安全・安心に対する消費者の信頼を高めます。
近年、消費者の食品安全への関心は高まっており、製品の履歴や安全性に関する情報開示が強く求められています。
単なる情報開示を超えて、消費者と生産者をつなぐストーリー性のある情報提供へと進化が求められており、これにより企業は顧客との信頼関係構築において差別化を図ることができます。
食品ロス削減に寄与できる
食品トレーサビリティシステムは、精密な在庫管理、賞味期限管理、先入れ先出しの徹底により、食品ロスを大幅に削減する効果があります。システムによるロット単位の管理で、賞味期限や消費期限の追跡が容易になり、期限切れによる廃棄リスクを低減できます。
また、システムによる先入れ先出しの自動管理は、倉庫や製造現場での作業ミスを防ぎ、古い在庫が取り残されるリスクを減らすことも可能です。
食品ロス削減は、廃棄コスト削減という経済的メリットと、環境負荷低減という社会的責任の両面で企業に価値をもたらします。複数拠点での在庫管理や、多品種少量生産を行う企業にとって、メリットは大きいといえるでしょう。
食品ロス削減に関しては、こちらの記事も参考にしてください。
企業のブランド価値が上がる
食品トレーサビリティシステムの導入と積極的な活用は、企業の品質管理体制と情報開示姿勢を示す証となり、ブランド価値向上に貢献します。
システムの存在自体が、企業の食品安全と品質管理への真剣な取り組みを示す証拠となり、「安全・安心な製品を提供する企業」というブランドイメージの確立につながります。
近年では、消費者だけでなく取引先や投資家も企業のリスク管理体制を重視する傾向が強まっており、トレーサビリティへの取り組みが重要な評価指標となっています。
企業はトレーサビリティシステムを単なるコスト要因ではなく、マーケティングや顧客コミュニケーションの観点からも活用することが重要です。
食品トレーサビリティシステム導入で気を付けたい課題
食品トレーサビリティシステムの導入には大きなメリットがある反面、取り組むべきいくつかの課題もあります。
- 初期導入や運用にコストがかかる
- データ入力・記録の負担が大きくなる場合がある
- 現場との連携・教育が難しい
- 製造工程の細部や現状はシステムのみで管理できない部分がある
- 緊急時の情報共有体制を構築する必要がある
- 情報漏洩やセキュリティのリスクがある
これらの課題に対する対応策についても把握しておきましょう。
初期導入や運用にコストがかかる
食品トレーサビリティシステムの導入には、ハードウェアやソフトウェア、コンサルティング費用などの初期投資に加え、保守費用や人件費などの継続的な運用コストが発生します。
自社サーバーでシステムを運用する場合は数百万円から数千万円の初期投資が必要になる場合があり、クラウド型でもユーザー数や機能に応じた月額料金が継続的に発生します。
また、バーコードリーダーやハンディターミナル、ラベルプリンタなどの周辺機器の購入費用も考慮しなければなりません。
中小企業にとってはコスト負担が大きく、投資回収の見通しが立ちにくい場合もあるため、課題に対応するために、段階的な導入アプローチが有効です。まずは優先度の高い製品ラインや工程から限定的に導入を始め、効果を確認しながら徐々に範囲を拡大して、初期投資を分散させましょう。
コストをなるべく抑えたい場合は、クラウド型システムの活用や必要最小限の機能からのスタートも検討してみてください。
データ入力・記録の負担が大きくなる場合がある
トレーサビリティシステムの導入には、原材料の入荷から製品の出荷までの各工程で詳細なデータ記録が必要です。従来の紙やExcelベースの管理からシステム化する過程で、データ入力の方法や頻度が変わることにより、現場作業者に新たな業務負担が生じます。
セーフィーが実施した食料品製造業の経営層・品質管理部門の責任者への調査によると、現状のトレーサビリティ体制に危機感がある人の半数が、入力・記録の負担が大きいと感じています。
導入初期や移行期には、慣れない操作や二重管理によって作業効率が一時的に低下する場合も少なくありません。
データ入力の負担を軽減するためには、バーコードやQRコードのスキャン、ハンディターミナルの活用など、可能な限り入力作業を自動化・簡素化することが必要です。既存の業務フローを分析し、必要最小限のデータ入力で最大限の効果が得られる設計を心がけましょう。
▼食料品製造業の経営層・品質管理部門の責任者への調査の詳細はこちら
現場との連携・教育が難しい
食品トレーサビリティシステムの導入を成功させるには、現場スタッフの理解と協力が不可欠です。
手書き・Excel管理に慣れた現場では、新システムへの抵抗感や操作習得の難しさがあります。IT機器の操作に不慣れな従業員やベテラン従業員から「これまでの方法を変えるのは面倒だ」「余計な仕事が増えてしまう」といった否定的な意見が出る可能性もあります。
この課題に対応するためには、まず導入の目的やメリットを丁寧に説明し、なぜ必要かを理解してもらうことが重要です。現場スタッフ自身にとってのメリットを具体的に示し、現場の意見を取り入れ、実際の業務フローに合った使いやすいシステムを構築しましょう。
製造工程の細部はシステムのみで管理できない部分がある
原材料の色合いや香り、食感などの官能評価はシステム化やデジタル化ができない領域です。製造工程の細部は作業者の技術や判断に依存する部分が大きく、完全なシステム管理が難しくなります。
トレーサビリティシステムの構築状況調査においても、「原材料の受入れから最終製品の出荷まで完全なトレーサビリティを確立」と回答したのは19.1%にとどまりました。
システムのみで管理できない部分の課題に対応するためには、「何を」「どこまで」システム化するかの適切な線引きが重要です。ミスが発生しやすい工程、データ管理が煩雑な部分を優先的にシステム化し、熟練者の判断や技術に依存する部分は、判断プロセスや結果を簡潔に記録する仕組みを設けるアプローチが有効です。
人とシステムのそれぞれの強みを活かし、相互に補完し合う形でトレーサビリティ体制を構築することが効果的です。
▼食料品製造業の経営層・品質管理部門の責任者への調査の詳細はこちら
緊急時の情報共有体制を構築する必要がある
食品事故や品質問題発生時には、トレーサビリティシステムで収集したデータをもとに、社内外の関係者と迅速かつ適切に情報共有を行う体制の構築が不可欠です。
システムは問題発生時の原因特定や影響範囲の把握に役立ちますが、食品事故への十分な対応とはなりません。特定された情報をもとに、社内の関連部門や取引先、消費者、必要に応じて行政機関などへ情報を伝達する体制が必要です。
実際は緊急時の情報共有に関して、「誰が」「どのような情報を」「どのタイミングで」「どの関係者に」伝えるべきかの明確なルールや手順が確立されていない企業も少なくありません。
万が一の食品事故や品質問題の発生を想定して、詳細な対応マニュアルの作成が重要です。
情報漏洩やセキュリティのリスクがある
食品トレーサビリティシステムには製造レシピや取引先情報、生産計画など企業の機密情報が蓄積されるため、データの改ざんや不正アクセス、情報漏洩といったセキュリティリスクへの対策が重要です。
トレーサビリティシステムは、製造プロセス全体の詳細な情報を網羅的に管理するため、企業の競争力に直結する機密情報が集約されています。クラウド型システムの場合、インターネットを介したアクセスが可能であるため、不正侵入のリスクが存在します。
内部関係者による意図的な情報持ち出しや、操作ミスによる情報漏洩のリスクも考慮する必要があるため、厳重な管理が必要です。場合によっては、多要素認証システムやデータの暗号化などの導入も検討しましょう。
食品トレーサビリティシステム導入の進め方
ここでは、食品トレーサビリティシステムを効果的に導入するための段階的なプロセスについて紹介します。 手順は以下の通りです。
- 導入計画を立てる
- 記録すべき項目とデータ管理方法を決定する
- 段階的に導入し現場への定着を図る
- 導入後の評価と継続的な改善に取り組む
各手順について、詳しく見ていきましょう。
1.導入計画を立てる
食品トレーサビリティシステム導入の第一歩は、自社の課題と目的を明確にした導入計画の策定です。「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることで、必要な機能や投資規模が見えてきます。
食品事故発生時の迅速な原因究明、業務効率化や廃棄ロス削減、法令遵守など、自社にとっての優先順位を決めましょう。導入計画には、現状の業務フロー分析や達成すべき具体的な目標や予算計画、推進体制と責任者、導入スケジュールを含めることが重要です。
システム選定では、自社の業務に合った機能をもつかどうか、食品製造業での導入実績、カスタマイズの必要性なども重要な判断基準になります。経営層や品質管理部門、製造部門など、関係者を巻き込んだプロジェクトチームを結成し、全社的な理解と協力を得られる計画を策定しましょう。
2.記録すべき項目とデータ管理方法を決定する
トレーサビリティシステムの中核になるのは、適切な記録項目の設定とデータ管理方法の決定です。
記録項目が多すぎると現場の負担が増大し、少なすぎると必要な情報が得られません。まずは法令で定められた最低限の記録要件を確認し、自社の品質管理上必要な項目を追加するのが効果的です。
以下が主な記録項目です。
| 記録項目 | 詳細情報 |
| 原材料の入荷情報 | 日時、メーカー、ロット番号、数量、品質検査結果 |
| 製造工程情報 | 製造日時、使用原料ロット、製造機器、担当者、製造条件 |
| 出荷情報 | 出荷先、出荷日時、製造ロット、数量 |
また、「5M1E」というフレームワークを活用し、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)、Measurement(測定)、Environment(環境)という視点で管理すべき情報を整理する方法も有効です。
データの保存期間は、食品の賞味期限や消費期限、法的要件を考慮する必要があります。食品衛生法に基づくHACCPの実施においては、厚生労働省のガイドラインにて「取り扱う食品の流通実態に応じて事業者が合理的な期間を設定する」ことが基本とされています。
実務上の目安として、多くの自治体や業界団体では原則1年間、賞味期限が1年以上の食品については賞味期限に一定期間を加えた期間の保存が推奨されています(※3)。
法令に則って、記録を管理・保存しましょう。
3.段階的に導入し現場への定着を図る
食品トレーサビリティシステムは一度に全社規模で導入するのではなく、特定のラインや工程、製品カテゴリーから段階的に導入し、現場への定着を図りながら範囲を拡大していくアプローチが効果的です。
段階的な導入には初期投資の分散や問題点の早期発見と修正、成功事例の社内共有による説得力の向上、現場スタッフが新システムに慣れる時間の確保といった利点があります。
段階的導入の典型的なステップは、以下の流れを意識してください。
- パイロットラインでの試験導入と評価
- 改善点の洗い出しとシステム調整
- 一次展開(主要ラインや製品)
- 二次展開(全社規模)
現場スタッフに「このシステムを使うと自分たちの仕事がどう良くなるのか」という実感を持ってもらうことが鍵になります。デジタル化に不安を感じている現場スタッフがすぐ慣れるよう、サポート体制を構築しましょう。
4.導入後の評価と継続的な改善に取り組む
食品トレーサビリティシステムの導入は、稼働開始がゴールではありません。定期的な評価と継続的な改善サイクルを通じて、長期的な価値を最大化することが重要です。
導入効果を客観的に測定するためには、導入前に具体的な成功指標(KPI)を設定しておくことがポイントです。評価すべき指標としては以下の点が挙げられます。
- トレース対応時間の短縮
- 原材料ロスの削減率
- 製造ミスの発生率の変化
- 棚卸作業時間の短縮
- 残業時間の削減
評価は定期的に行い、数値データだけでなく現場の声や気づきも重視しましょう。また、蓄積されたトレーサビリティデータを分析することで、業務改善に繋がる洞察を得ることも可能です。
映像記録による食品安全管理と品質保証の強化|日世株式会社
ソフトクリームの総合メーカーである日世株式会社は、製造工程の可視化と品質保証体制の強化のため、全国7カ所の工場に 「Safie(セーフィー)」を導入しました。
同社はフードディフェンスと品質管理を重視し、以前からオンプレミス型のカメラシステムを利用していましたが、定期的なHDDの更新作業や録画データを確認するために現地へ行く必要があるなど、運用面に課題がありました。また、保存容量の問題から画質やフレームレートを落として録画していたため、映像の鮮明さにも課題を感じていました。
これらの課題を解決するため、高画質・高フレームレートの映像を長期間クラウドに保存でき、導入費用とランニングコストを抑えられるSafieの導入を決定しました。
導入後は、原料保管から調合、焼成、検品、洗浄まで製造ラインのあらゆる工程を撮影し記録することで、製造プロセスの透明性を確保しています。「製造ラインを網羅した映像がクラウドに残って確実・手軽に視聴できるようになり、品質保証や食品ロス軽減の体制が強化された」と評価しています。
特に、イレギュラーな事態が発生した際に映像で過程を追えることで、影響範囲を早期に特定できるようになりました。例えば備品紛失時に「製品に混入したのか、ごみ箱に落ちたのか」といった経緯を映像で確認できるため、不必要な製品廃棄を防止し食品ロス削減にも貢献しています。
※この事例は直接的なトレーサビリティシステムではありませんが、映像による製造工程の記録は、問題発生時の原因究明と影響範囲の特定に役立ち、食品安全管理を強化する有効な手段といえるでしょう。
食品トレーサビリティを安定して運用するためにはSafieのクラウド録画サービスがおすすめ
食品トレーサビリティ実現のうえで、Safieのクラウド録画サービスが適している理由は「法令遵守」の観点にあります。
食品トレーサビリティでは、法令によって一定期間の記録保存が義務付けられている点に注意しましょう。牛トレーサビリティ法や米トレーサビリティ法では原則として3年間、膨大なデータを安全に保管する必要があります(※4、※5)。
Safieのようなクラウド録画サービスは、データをオンラインで安全に長期保存でき、自社でサーバーを維持管理するコストや手間を削減できる利点があります。
また、Safieのクラウドカメラは、設置が簡単で専門知識なしで導入可能なため、段階的にシステムを拡張できる点が魅力です。製造ラインの各工程にカメラを設置することで、原材料の投入から製品の包装までを一貫して記録し、後から検証することが可能になります。
クラウド録画サービスについては、サービス資料で詳しく紹介しているので、気になる方はぜひダウンロードしてみてください。
▶クラウド録画サービス「Safie」のサービス資料の無料ダウンロードはこちら
食品トレーサビリティシステムの実現で安全性と信頼性を高めよう
食品トレーサビリティシステムは、製品の原料調達から製造、出荷までの履歴を追跡できる仕組みで、食品事故発生時の迅速な対応や消費者信頼の向上や食品ロス削減に貢献します。
導入には初期コストや運用負担がかかりますが、段階的な実施と現場へのメリット提示で効果的に定着させることが可能です。法令対応や経営改善の視点から導入を検討する際は、自社の状況に合った選定と導入計画を練る必要があります。
セーフィーは、映像ソリューションを提供している企業です。
適切なシステム選びと運用で、食の安全性と企業価値を高められます。セーフィーのクラウドカメラを導入し、問題発生時の対応精度を高め、品質管理の体制を大幅に改善できた例も多数あります。食品のトレーサビリティ強化を検討している方は、ぜひお気軽にセーフィーへご相談ください。
- 食品製造業における品質管理の実態調査レポート
- 食料品製造業の経営層・品質管理部門の責任者110名に、品質管理の実態調査を実施したレポートです。
※1 出典:“牛・牛肉のトレーサビリティ”.農林水産省.令和7-03-03(参照 2025-08-08)
※2 出典:“安全の安全確保に向けた取組(P4、7)”.厚生労働省.(参照 2025-08-08)
※3 出典:“食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について”.厚生労働省.2003-08-29(参照 2025-08-08)
※4 出典:“牛トレーサビリティ法 個体識別番号の伝達・表示(P1)”.全国食肉事業協同組合連合会.(参照 2025-08-08)
※5 出典:“食品のトレーサビリティ制度(P8)”.国立国会図書館.2012-12-27(参照 2025-08-08)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。