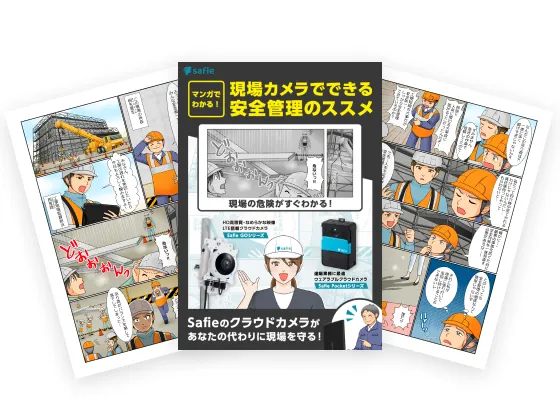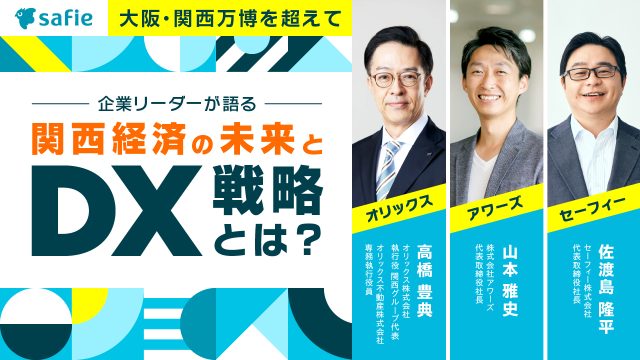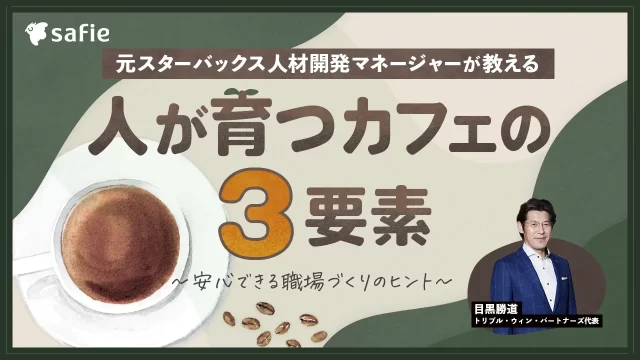建設現場(工事現場)では、死亡事故を含む死傷災害が多く発生しています。重大事故を未然に防ぐためには、状況に合わせた対策が必要です。
本記事では、建設現場(工事現場)での事故発生状況や事故の内容、発生する原因、効果的な対策などを紹介します。さらに、事故対策のひとつであるクラウドカメラの導入について、おすすめの機種や導入事例を紹介しますので参考にしてください。
目次
建設現場(工事現場)での事故発生状況
工事現場を含む建設現場では、さまざまな事故が発生します。未然に防ぐためにも、どのような内容の事故が生じているのかを把握することが大切です。以下に、厚生労働省から発表された過去5年間の労働災害を表にまとめました。
表1:建設業における労働災害(死傷災害)の発生状況(件数)
| 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | 挟まれ・巻き込まれ | 交通事故 | その他※ | 合計 | |
| 2019年 | 5,171 | 1,589 | 695 | 1,431 | 482 | 842 | 1,693 | 568 | 2,712 | 15,183 |
| 2020年 | 4,756 | 1,672 | 704 | 1,370 | 452 | 791 | 1,669 | 547 | 3,016 | 14,977 |
| 2021年 | 4,869 | 1,666 | 690 | 1,363 | 447 | 825 | 1,676 | 508 | 4,035 | 16,079 |
| 2022年 | 4,594 | 1,734 | 684 | 1,318 | 428 | 800 | 1,706 | 486 | 2,789 | 14,539 |
| 2023年 | 4,554 | 1,598 | 643 | 1,234 | 431 | 781 | 1,704 | 531 | 2,938 | 14,414 |
表2:建設業における労働災害(死亡災害)の発生状況(件数)
| 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | 挟まれ・巻き込まれ | 交通事故 | その他※ | 合計 | |
| 2019年 | 110 | 6 | 1 | 18 | 34 | 26 | 16 | 28 | 30 | 269 |
| 2020年 | 95 | 6 | 2 | 13 | 27 | 13 | 27 | 38 | 37 | 258 |
| 2021年 | 110 | 5 | 1 | 10 | 31 | 19 | 27 | 26 | 59 | 288 |
| 2022年 | 116 | 8 | 0 | 16 | 27 | 27 | 28 | 25 | 34 | 281 |
| 2023年 | 86 | 8 | 2 | 21 | 18 | 10 | 13 | 25 | 40 | 223 |
※その他に含まれる災害種類:踏抜き、おぼれ、高温・低温物との接触、有害物との接触、感電、爆発、破裂、火災、動作の反動・無理な動作、分類不能
表1の死傷災害とは、死亡災害および休業4日以上の災害のことです。表2の死亡災害とは、人が亡くなった重大な災害を指します。
これら表からみると、死傷災害の件数は、2019〜2023年の5年間はほぼ横ばいで推移しています。死亡災害の件数については、2019〜2022年の4年間は横ばいですが、2023年は減少しています。
建設現場(工事現場)で発生する事故の内容
建設現場(工事現場)で発生する事故の内容を把握すると、対策が立てやすくなります。とくに現場との関連性が高いものは注意しましょう。
ここでは、どのような事故が発生しているのか、先述した表の内容を参考に解説します。
墜落・転落事故
建設現場(工事現場)で発生する事故で多いのが、墜落・転落事故です。上述した事故の発生状況を見てもわかるように、事故の種類のなかでは最も多くなっています。
墜落と転落は似た言葉ですが、厳密には異なります。墜落とは高いところから落ちることに対して、転落とは転げ落ちることです。足場から身体が完全に宙に浮いた状態で落下すると墜落になり、階段から転げ落ちると転落となります。
高所作業の多い建設現場(工事現場)では、とくに目立つ事故です。本人が怪我をするだけでなく、ほかの人も巻き込む恐れがあり、重大な事故になりかねません。墜落・転落事故の対策は、優先度が高いといえるでしょう。
転倒事故
転倒事故も、建設現場(工事現場)で発生する事故のひとつです。転倒事故とは、何かに足を引っかけてつまずいたり、足を滑らせて転んだりする事故をいいます。
現場では屋外だけでなく屋内でも床が平らでない箇所が多々あり、またその状態が長期間続くため、注視しながらの作業が必要です。しかし実際には、配管や床に置かれた資材につまずいたり、泥などに足をとられ転倒したりする事故が少なくありません。
死亡災害件数は少ないものの、死傷災害件数が多くなっていることから、十分な対策が必要です。
激突事故
建設現場(工事現場)で発生する事故のうち、激突事故も頻繁に発生します。激突事故とは、たとえばドラグショベルの作動範囲にいた作業員がバケットに激突するといった事故です。些細な接触でも衝撃が大きいため、重大な事故につながります。
飛来・落下事故
建設現場(工事現場)では、飛来・落下事故も少なくありません。飛来・落下事故とは、置いてあった資材や道具が強風に飛ばされ、人に接触して生じる事故のことです。
屋外の現場では、強風に晒される場所が数多くあります。強風に飛ばされた資材や建設機材が、落下することは珍しくありません。クレーンやショベルカーといった建設機材の一部が落下すると重大事故となるため、厳重な対策が求められます。
崩壊・倒壊事故
建設現場(工事現場)では、崩壊や倒壊に伴う事故が多発しています。主に現場内の建築物や足場が崩れたり、解体中の建物が倒れたりすることで引き起こされ、発生件数に対して死亡者が多い点が特徴です。
崩壊・倒壊事故が起きる原因は、対象物が安定性を欠いていることです。具体的には、ブロック塀や解体中のコンクリート壁が倒れ、作業員が下敷きになるケースなどが報告されています。
現場で作業している作業員だけでなく、現場近くの通行人にも被害が及ぶ可能性があります。
激突される事故
激突される事故も、建設現場(工事現場)ではよく発生する事故です。上述した激突事故と似ていますが、激突事故は人が物にぶつかっていく事故で、「激突され」は重機などの物のほうが人にぶつかる事故のことで異なります。
建設現場(工事現場)では、クレーンやブルドーザーなどの重機が欠かせません。しかしこのような重機が、作業員に激突する事故は頻発しており厳重な対策が必要です。
コンクリート圧砕機から外れたアタッチメントが作業員の頭部に激突し、作業員が死亡するという痛ましい事故も起こっています。少しの接触でも、大きな事故になりやすいのが特徴です。
挟まれ・巻き込まれ事故
建設現場(工事現場)では、作業員が機械や設備に挟まれたり巻き込まれたりする事故が頻繁に発生しています。たとえば、重機とダンプの間に体が挟まれるケースや、機械の部品やベルトに巻き込まれるケースなどです。挟まれ・巻き込まれ事故によって毎年多くの作業員が怪我を負っており、被害が後を絶ちません。
交通事故
交通事故も建設現場(工事現場)でよく見られる事故です。ほかの事故に比べて発生件数は少ないものの、死亡件数の多さが目立ちます。
交通事故は、建設現場(工事現場)だけで生じているわけではありません。公道でも発生しうるため、被害者は作業員だけでなく一般人も含まれます。また作業をしている作業員が、公道を走っている一般車にはねられるケースもあり、作業中の交通事故対策は必須です。
建設現場(工事現場)で事故が発生する原因
ここでは、建設現場(工事現場)で事故が発生する原因を紹介しましょう。現場では、ヒューマンエラーや現場における環境、機器の誤作動などさまざまな原因で事故が発生しています。どのような原因があるのかを確認してください。
作業員の注意不足
建設現場(工事現場)で事故が生じる大きな原因のひとつは、作業員の注意不足でしょう。現場で働く作業員の不注意や油断は、大きな事故につながりやすくなります。
現場の安全対策不足
現場の安全対策不足も建設現場(工事現場)で事故が発生する原因といえるでしょう。たとえば、高所での作業場に手すりがなかったり足場が老朽化していたりと、現場の環境そのものが原因となるケースです。また、現場が散乱していることも事故の原因となるため、日頃から整理整頓が欠かせません。
作業員の管理不足
建設現場(工事現場)で事故が発生する原因に、作業員の管理不足があります。たとえば人手が足りなかったり、作業員に長時間労働を強いていたりといったケースです。このような環境のもとでは、作業員は体調不良や過労で注意力や集中力が低下します。判断力が鈍り、事故につながりやすくなるため注意が必要です。
機器・道具の欠陥や不備
機器・器具の欠陥や不備も、建設現場(工事現場)における事故の原因となります。機器や道具は、正常に作動するのかを確認する定期的な点検や整備が必要です。このような安全対策を怠ると、重大な事故を誘引します。
建設現場(工事現場)の事故を防ぐ対策とは
ここでは、建設現場(工事現場)の事故を防ぐ対策を紹介します。事故を未然に防ぐには、従業員がヒューマンエラーをしない取り組みや安全な労働環境を整えることが重要です。
機器・道具の点検や整備
建設現場(工事現場)の事故を未然に防ぐには、機器や道具の点検・整備が必須です。作業に使う道具面での故障や欠陥は、重大事故を招きかねません。
繰り返しの作業となりますが、点検作業や整備は2人以上でおこなうことが求められます。安全に作動するかどうかをきちんと確認し、安全管理を徹底することが重要です。
また、事故防止のための取り組みも進めましょう。たとえば重機にバックセンサーや挟まれ防止バーを取り付けると、挟まれ事故や巻き込まれ事故を未然に防げます。
安全意識を高める教育の実施
従業員の安全意識を高める教育は、事故を防ぐ対策として効果的です。従業員が作業に慣れてくると、安全意識が薄まります。ヒヤリハットの事例を周知し、少しの油断が事故につながることを意識してもらうことが大切です。ヒヤリハットとは、事故になりかけたものの、幸いにも事故や災害に至らなかった事象をいいます。
安全意識の向上のためには、日頃のKYT(危険予測訓練)が不可欠です。KYTとは、現場で生じかねない事故に対して、具体的な対処法を実際に訓練することです。KYTを繰り返すことで、従業員の安全意識が自然と高まります。
現場のパトロール強化
事故を未然に防ぐには、現場のパトロール強化が重要です。作業員が決められた安全装備を着用しているかどうか、また従業員の体調はどうかなど、パトロールしながら現場の状況や作業員の様子などを丁寧に確認する必要があります。
クラウドカメラの活用
建設現場(工事現場)の事故を未然に防ぐために、クラウドカメラの活用が効果的です。クラウドカメラとは、インターネットに接続して、撮影した映像をクラウド上に保存するカメラをいいます。
遠隔から必要な箇所をズームで確認できたり、複数人で映像を視聴できたりと、安全対策として有用です。万が一、事故が発生した際には、映像をもとに原因を探り有効な対策を立てられます。
安全対策におすすめのクラウドカメラ
建設現場(工事現場)の安全対策におすすめのクラウドカメラは、次の3つです。
- Safie GO 360(セーフィー ゴー サンビャクロクジュウ)
- Safie GO PTZ Plus(セーフィー ゴー ピーティーゼット プラス)
- Safie Pocket2 Plus(セーフィー ポケットツー プラス)
それぞれSIM搭載のため単体でインターネット通信が可能。固定カメラの「Safie GOシリーズ」は電源を挿すだけ、バッテリー搭載のウェアラブルカメラ「Safie Pocket2 Plus」は電源を入れるだけで撮影・録画を始められます。
それぞれの機能や活用方法を解説します。
Safie GO 360
「Safie GO 360」は、360度全方位を撮影できるクラウドカメラです。とくに、建設現場(工事現場)全体を俯瞰して、管理したい場合に有用です。左右だけでなく上下にも広い画角があり、区画を区切って上下作業をしているときの安全管理にもおすすめです。IP66の防水・防じん性能のため、屋外の厳しい環境下でも問題なく作動します。

Safie GO PTZ Plus
「Safie GO PTZ Plus」は、レンズを上下左右に自由に動かせるパン・チルト機能を搭載しているカメラです。光学ズームも可能で、離れた作業エリアを細部まで確認したいといった場合に重宝します。
たとえば、高所で作業する作業員は安全帯のフック掛けをしているかどうか、高所に張られたネットに穴や隙間はないかなどを遠隔で確認できます。安全管理は細かい部分のチェックが欠かせないため、細部まで確認できるカメラは現場でも重宝するでしょう。
また、GPS機能もついており、広い現場でもどこのカメラの映像なのか、素早い確認が可能です。

Safie Pocket2 Plus
「Safie Pocket2 Plus」はウェアラブルタイプで、作業着やヘルメットに取り付けて利用できるカメラです。また三脚設置や単管などへ固定することも容易で、さまざまな使い方ができます。バッテリー付きで持ち運びが簡単なため、短時間で作業エリアが移動する現場で役に立つでしょう。
また、通話機能が搭載されており、同じ映像を共有しながらコミュニケーションが取れるのもポイントです。作業員が作業中に判断に迷う場面があった際は、映像を共有しながら監督者と通話ができれば、より安全かつ安心して取り組むことができます。

クラウドカメラの導入事例
ここでは、セーフィーのクラウドカメラを導入した事例を3つ紹介します。各社が、どのようにクラウドカメラを活用しているのかを参考にしてください。
清水建設株式会社
清水建設株式会社は、広大な現場の安全管理にSafie GO PTZを導入しています。工区内に19台のカメラを設置し、工事進捗に合わせて、管理したいポイントにカメラを移設して利用しています。
特殊・重要な作業の際には、本部の安全管理部門が、遠隔からリアルタイムでサポートしています。不安行動が察知された場合は、即座に映像にコメントをつけて現場に知らせるなど、遠隔での安全管理に役に立っているとのことです。
また、SIM搭載で通信ケーブルが不要で設置できる点も高く評価しています。
鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社は、大規模な建設現場での安全管理の効率化を目的に、施工エリアや工事車両の出入口、外部の通路のそれぞれに複数台のカメラを設置しています。その結果、事務所や支店などの遠隔から、危険度が高い作業場や立入禁止エリアをカメラで確認することが可能となりました。
災害時の被害状況の確認にもクラウドカメラは活躍しており、迅速な初動対応ができるようになったと高評価です。
東北電力株式会社
東北電力株式会社は、労災ゼロを目指し、より多くの人が日常的かつ効率的に安全パトロールができるようにとクラウドカメラを導入しています。クラウドカメラにより、実際の作業の様子を社員がリアルタイムや録画で確認し、安全パトロールを遠隔から実施することが可能となりました。
不安全行為や注意点が見つかると、録画映像を添えて現場の安全主査に報告し、関係者に周知しているとのことです。
建設現場(工事現場)での安全対策にセーフィーのクラウドカメラが効果的
建設現場(工事現場)では、死亡事故を含む死傷災害が多数発生します。事故を未然に防ぐためには、作業員の安全意識を高める教育や機器・道具の点検・整備、現場のパトロールが欠かせません。ほかにも、クラウドカメラの導入も効果的です。
セーフィーのクラウドカメラには、さまざまなタイプがあります。建設現場(工事現場)で利用しやすい360度全方位を撮影できるものやウェアラブルタイプのものなど、現場の課題解決に役立つでしょう。安全対策のひとつとして、セーフィーのクラウドカメラをぜひご検討ください。
- マンガでわかる!現場カメラでできる安全管理のススメ
- 現場カメラを使った遠隔からの安全管理の方法やメリット、活用シーンをマンガでわかりやすく解説します。
※1 出典:“労働災害発生状況”.厚生労働省.(参照 2025‐2‐25)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。