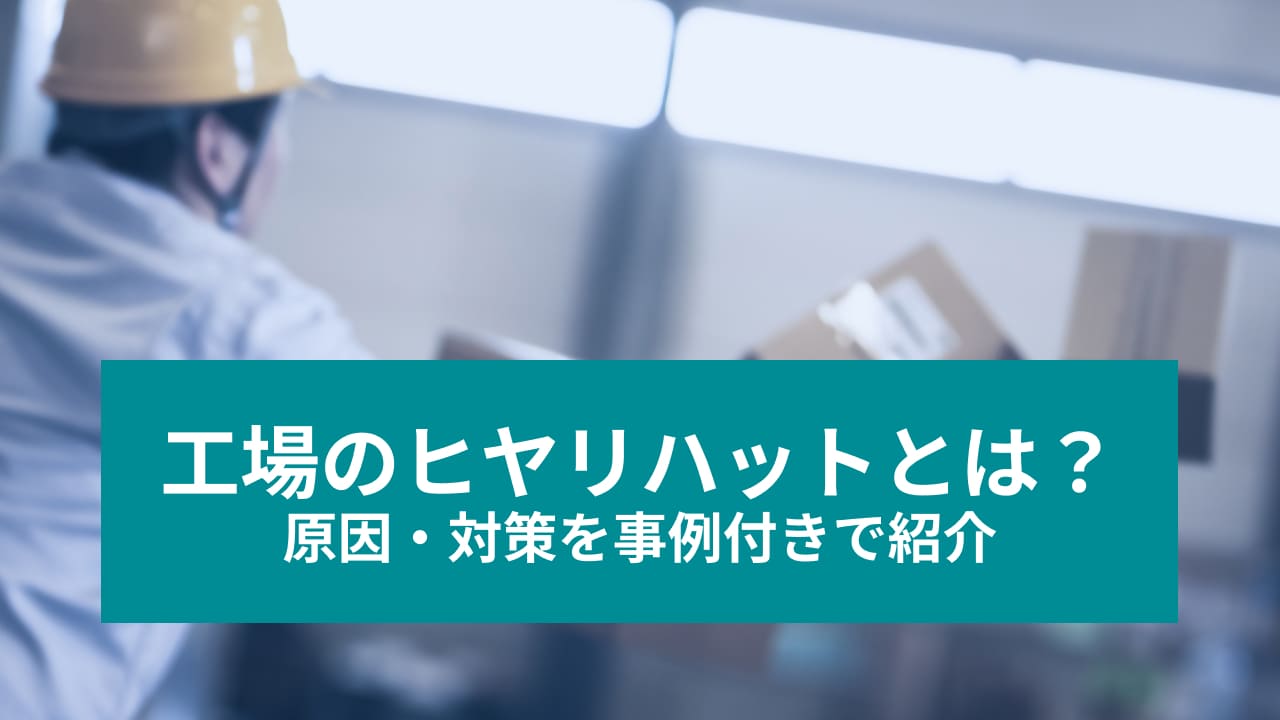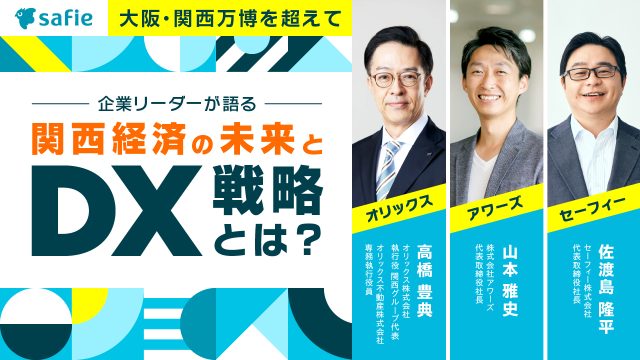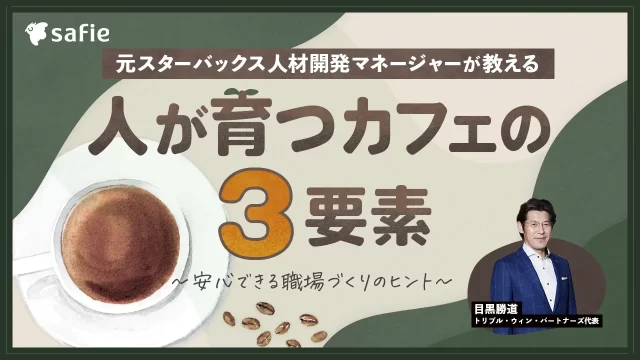ヒヤリハットとは、事故や災害につながりかねない軽微な出来事を指します。ヒヤリハットだからといって甘く見ることなく、原因と対策を知ることで、重大な事故の防止が可能です。本記事では、工場におけるヒヤリハットの現状と、具体的な事例を紹介します。
目次
ヒヤリハットとは?
ヒヤリハットとは、一歩間違えると事故や災害につながる出来事のことです。「危なかった」とヒヤリとしたり、「危ない!」とハッとしたりすることに由来します。
ヒヤリハットは、大事には至らなくても、対応を誤っていれば事故や災害につながりかねないものです。ヒヤリハットの発生状況について把握し、同じヒヤリハットを繰り返さないようにすることで、重大な事故や災害を防止できます。
2023年の労働災害統計(※1)によると、製造業における死亡災害は138件であり、建設業の223件に次ぐ多さです。死亡だけでなくケガを含めた死傷災害については27,194件と、建設業の14,414件の約2倍にのぼりました。
機械や工具を利用してさまざまな作業を行う工場では、とくにヒヤリハットが発生しやすいため、内容を把握して対策を取る必要があります。
工場で発生するヒヤリハットの事例
2023年の労働災害統計(※1)によると、製造業に多かった事故の種類は以下の通りです。
- はさまれ・巻き込まれ
- 転倒
- 動作の反動・無理な動作
- 転落・墜落
- 切れ・こすれ
死亡災害については、以下の種類も多くなっています。
- 崩壊・倒壊
- 飛来・落下
- 激突され
以下では、工場で発生しやすいヒヤリハットの事例を種類別に紹介します。
はさまれ・巻き込まれ
はさまれ・巻き込まれにおけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 資材運搬用のリフト・エレベーターに頭を挟まれそうになった
- フォークリフトがバックしてきたときに壁との間に挟まれそうになった
- 金属加工機械に体や衣服が巻き込まれそうになった(横中ぐり盤・ボール盤・プレス機など)
- ミキサーや生地練り機に体や衣服が巻き込まれそうになった
- ベルトコンベアのローラーに身体や衣服が巻き込まれそうになった など
さまざまな機械を使う工場では、操作の誤りやタイミングの悪さ、不注意などによって機械に身体が挟まれそうになったり、衣服が巻き込まれたりといったヒヤリハットが発生しやすい傾向にあります。
転倒
転倒におけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 冷蔵庫内の霜で滑り転倒しそうになった
- 誤って台車を踏んでしまい転倒しそうになった
- 濡れた床で足が滑り転倒しそうになった
- 熱湯や熱いものを運んでいるときに転倒しそうになった
- クリーンルームの粘着マットに足を取られ転倒しそうになった など
工場では、重いものや危険物を持ち運ぶ機会も多くあるため、転んでしまわないよう足元に注意する必要があります。
動作の反動・無理な動作
動作の反動・無理な動作におけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 重いものを動かそうとして力を込めたところ、腰に痛みが走った
- 長時間同じ姿勢だったため身体を伸ばしたら腰に違和感を覚えた
- 重いものを運んでいるときに呼び止められて振り返り、背中をひねった など
工場では力仕事をしたり、同じ体勢を長時間続けたりする局面もあるため、体の一部に負担がかかり痛みが生じることもあります。
転落・墜落
転落・墜落におけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- フォークリフトやオーダーピッキングリフトでの作業中に転落しそうになった
- 脚立を使って材料・製品を取るときに落ちそうになった
- 荷降ろし・荷積みの際にトラックから落ちそうになった
- 台車とともに段差から落ちそうになった など
工場では高い位置に材料や製品を置く場合もあるため、作業中に高所から転落・墜落するヒヤリハットは多く起こっています。
切れ・こすれ
切れ・こすれにおけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 誤操作によって電動ノコが突然動き出した
- 食材を切る機械の刃に指が触れそうになった など
工場の機械の中には、鋭い刃を持つものや高速で動くものもあるため、細心の注意を払わなければなりません。
崩壊・倒壊
崩壊・倒壊におけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 積んでいた商品や材料が崩れて体に当たりそうになった
- 台車が倒れて下敷きになりそうになった
- 機械やその一部が倒れてきて当たりそうになった など
高く積み上げた材料や製品が崩れ落ちてくることは、工場でよく起こるヒヤリハットです。台車やかご台車を置くときにも、不安定にならないよう注意しましょう。
飛来・落下
飛来・落下におけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 金属加工で発生したキリ粉が飛んできて目に入りそうになった
- 切断した材料や加工中の材料が落ちた・飛んだ
- 高所から材料や製品の箱が落ちてきた
- 手が滑り持っていた材料が足の上に落ちそうになった など
工場では、切断した材料や作業くずが思わぬ方向・場所に飛んだり落ちたりすることへの備えが必要です。重いものを落としてしまう、高所からものが落下してくるという可能性もあります。
激突され
激突されにおけるヒヤリハットの例は、次の通りです。(※2)
- 重い荷物を載せたかご台車にぶつかりそうになった
- フォークリフトや荷物が移動してきてぶつかりそうになった など
重量のあるものが動いている工場内では、激突されも発生しやすいヒヤリハットの1つです。
その他
工場においては上記のほか、次のようなヒヤリハットが起こることもあります。(※2)
- 高温の鉄板を素手で触ってしまった
- 高温の油に入った水分が跳ねて飛んできた
- 加工機械の清浄中に蒸気が噴き出て火傷しそうになった など
工場でヒヤリハットが起こる原因
工場におけるヒヤリハットの原因は、以下のようにさまざまです。
- 安全な環境が整っていない
- 適切な手順についての情報共有ができていない
- 作業者の技術が不足している
- 身体面・精神面から作業に集中できない
- 安全意識が低い
整理整頓や死角・段差への対応ができていなければ、工場内の環境は安全とはいえません。「じゅうぶんな確認ができていない」「機械や器具の使い方が不適切」など、作業工程に関する原因もあります。
寝不足や体調不良など、作業者の個人的な理由によってヒヤリハットが起こる可能性もあるでしょう。働き始めて間もない場合に、技術や知識が少ないこともヒヤリハットの原因になりえます。
工場のヒヤリハット対策6選
原因を踏まえて、以下の対策によって工場のヒヤリハットを防止しましょう。
- 確認や点検を徹底する
- 作業手順を定めて周知する
- 報告書による共有体制を整える
- KYT(危険予知トレーニング)を実施する
- 作業者の体調管理に努める
- 安全確認にカメラを活用する
それぞれの対策方法について、以下で具体的に紹介します。
確認や点検を徹底する
作業を始める前に、安全確認や設備の点検を徹底することが大切です。作業手順に確認や点検を組み込み、習慣づけるとよいでしょう。
作業員に確認や点検の重要性を意識づけることも必要です。以下のような方法が考えられます。
- 作業内容の注意点や着用すべき保護具について工場の入口に写真付きで掲示する
- 従業員から安全標語を募集し、優れているものを休憩室に掲示する
- 朝礼や始業時に安全のための基本事項を唱和する
確認や点検を惰性で行わないようにするためにも、安全意識向上の取り組みが必要です。
作業手順を定めて周知する
作業の安全な手順を定め、周知しましょう。ヒヤリハットの事例をもとに、「自社でも同じようなことが起こるリスクはないか?」と考え、機械の操作や業務の手順を安全なものに見直すことが大切です。
手順におけるチェックリストの記入を業務に組み込んだり、正しい手順をわかりやすく掲示したりして、周知徹底に努めましょう。
業務のマニュアルを作ることも有効な方法です。マニュアル作成の方法については、以下を参考にしてください。
報告書による共有体制を整える
発生したヒヤリハットを報告・共有することで、同様のヒヤリハットの再発を防止できます。実際に起こったヒヤリハットとその原因、再発しないための対策を盛り込んだフォーマットにすることで、報告者の意識向上が可能です。
報告されたヒヤリハットの内容は、社内で共有しましょう。他の作業者や監督者・責任者とヒヤリハットを共有する時間を設けることで、社内全体の意識向上につながり、重大事故の防止が期待できます。
KYT(危険予知トレーニング)を実施する
KYTとは、工場に潜む危険や問題についてチームで議論し、危険の回避や問題解決の能力を高めるトレーニング方法です。一人ひとりが考える機会となり、安全意識の向上が期待できます。
ヒヤリハットの共有は、実際に起こった事例をもとに対策方法を考える対策方法です。一方KYTでは、工場で起こりうるヒヤリハットや事故にはどのようなものがあるのかを考え、実際に発生しないよう対策します。KYTによって危険を察知する能力が磨かれるでしょう。
KYTについて詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
作業者の体調管理に努める
作業者が健康な状態で業務に臨めるよう、配慮も必要です。具体的には、次のようなことを採り入れましょう。
- 休憩・水分補給の時間の確保
- 体温・健康状態のチェック
- 長時間労働を避けるためのシフト調整
会社側だけでなく、作業者一人ひとりが健康に対する意識を持つことも大切です。健康に関する掲示を行い、作業者の意識を高めることも検討しましょう。
安全確認にカメラを活用する
工場の安全を管理してヒヤリハットを防止するためには、カメラの設置も効果的です。カメラで工場内を確認できれば、機械の不具合や作業中の危険をいち早く察知し、対策ができます。
工場の様子をリアルタイムで確認するなら、セーフィーのクラウドカメラがおすすめです。屋内用・屋外用のさまざまなカメラをそろえており、自社の環境に合ったものが見つかるでしょう。
角度の変更やズームができるもの、180度・360度見渡せるものなどがあるため、見たい場所や使い方によって選べます。死角となる場所や危険が発生しやすい場所に設置することで、離れた場所からでもリアルタイムで工場内を確認できるため、ヒヤリハットの防止に役立つでしょう。
おすすめのカメラについては、以下の記事を参考にしてください。
ヒヤリハットの報告を定着させるポイント
ヒヤリハットが起こっても、「後ろめたい」「報告するのが面倒」という理由で作業者が報告書を提出しないことも考えられます。しかし、ヒヤリハット対策は重大な事故や災害を防止するために行うものであり、継続することが大切です。以下では、ヒヤリハットの報告を定着させ、安全な工場にするためのポイントをみていきましょう。
報告しやすいフォーマットにする
報告書は作業者が記入しやすく、必要な記載事項に絞ったものを準備しましょう。記入に負担のかからないシンプルなものにすると、記入への抵抗を減らせます。記載事項には、起こったヒヤリハットの内容・原因・対策法は最低限必要です。
評価制度や報奨金を設ける
報告をプラスに反映する評価制度や報奨金を設けることも、ヒヤリハット報告の定着に有効です。ヒヤリハットの報告者にとってのメリットがあれば、積極的な報告が増えると考えられます。
ヒヤリハットは危険の一歩手前の状態であるため、「責任を問われたり不注意とみなされたりして評価が下がるのでは?」と心配する作業員もいるかもしれません。作業員にはヒヤリハットの重要性とともに、報告によって評価が下がる心配はないことを伝えましょう。
情報共有の時間を定期的に確保する
ヒヤリハットについて共有し、考えるための時間を設けることも大切です。
通常の業務が忙しい中では、一人ひとりがヒヤリハットや工場の危険について考えることは難しいでしょう。業務時間内にヒヤリハット対策のための時間を確保することで、作業者は無理なく安全対策に向き合えます。
一人ひとりが安全意識を高めることで、ヒヤリハット報告の重要性を理解できるようになり、報告の習慣づけにも役立つでしょう。
ヒヤリハットを防止して安全な工場へ
ヒヤリハットとは、重大な事故や災害には至らなかったものの、その兆候として発生する出来事のことです。機械を使った作業や力仕事の多い工場においては事故が起こりやすいため、ヒヤリハットを報告・共有して事故防止に努める必要があります。
工場のヒヤリハットには「はさまれ・巻き込まれ」をはじめさまざまなパターンがあるため、具体的な事例を知って自社でも同様の危険性がないかを考えることが大切です。対策として、確認や点検、作業手順のマニュアル化、KYTなどを行いましょう。報告体制を定着させることも、ヒヤリハットや事故の継続的な防止に役立ちます。
- 製造業界向けクラウドカメラ活用ガイド
- 製造業界におけるクラウドカメラの活用方法と導入事例をご紹介しています。
※1 出典:“職場のあんぜんサイト:労働災害統計”.厚生労働省.(参照 2025-2-24)
※2 出典:“職場のあんぜんサイト:ヒヤリ・ハット事例”.厚生労働省.(参照 2025-2-24)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。