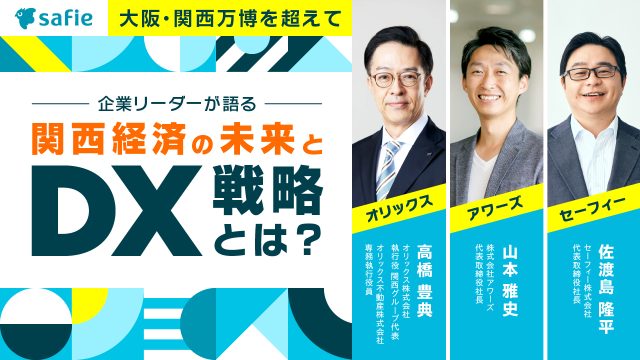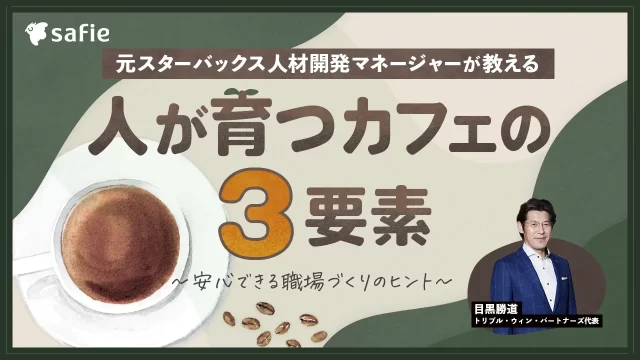トラックやタクシーの運転手など、多くの職種で必須な点呼。国土交通省は、この点呼を自動化する目的で機器認定制度を創設し、2023年1月より業務後自動点呼(乗務後自動点呼)の運用を始めました。業務後自動点呼のメリットやデメリット、導入方法について分かりやすく解説します。
※監修者:行政書士法人シグマ 代表 行政書士 阪本 浩毅
※本記事の内容は公開時点の情報です。
目次
自動点呼とは?
自動点呼とは、運転手が乗務前後に点呼執行者と行う点呼業務を、AIやロボット、ICT機器を活用して自動化する点呼方法です。
点呼執行者の代わりにロボットやICT機器が代替することで、一部の業務負担の軽減による労働時間の削減や、点呼ミスの防止による安全性の向上などが期待されます。
その他の点呼の種類と内容
自動点呼以外にも点呼にはさまざまな種類があり、必要なタイミングや実施場所は異なります。それぞれの点呼方法について1つずつ紹介します。
・対面点呼
・電話点呼
・IT点呼
・遠隔点呼
対面点呼
営業所または車庫の定められた場所で運転手と点呼執行者が直接対面して行う点呼方法です。乗務前と乗務後に、酒気帯びの有無の確認、運転手の疾病、疲労、睡眠不足などの状況を確認します。点呼の記録は点呼記録簿に記載し、1年間の保存が必要です。
電話点呼
運転手と点呼執行者が電話で点呼を行う方法です。運転手が遠隔地で乗務開始・終了する場合にのみ認められます。乗務前後のどちらも電話点呼となった場合には、中間点呼の実施も必要です。電子メールやFAXの利用、自社であっても他の営業所に所属している運転手への点呼は認められていません。
IT点呼
インターネットを介してカメラ付きのパソコンやスマートフォンなどのICTを利用して行う点呼方法です。業務前点呼、中間点呼、業務後点呼のいずれにおいても、条件を満たした上で国土交通省で認定された点呼機器を使えば非対面で実施できます。
同一事業者内の「Gマーク(※1)」を取得した営業所において、各営業所間または営業所と車庫間で実施できます。なお、営業所間の実施は、1営業日のうち連続した16時間以内に限られます(営業所とその車庫間は時間制限はありません)。
※1 Gマーク:「安全性優良事業所」として認定された事業所に付与されるマークで、安全基準をクリアしていることを示す認定資格です。法令遵守、事故や違反の状況、安全対策の取り組みが評価基準となります。
▼IT点呼についてはこちらで詳しく解説しています。
遠隔点呼
一定の基準を満たした機器やシステムを利用し、営業所間・車庫間・完全子会社(親会社が100%の株式を有している子会社)などの離れた場所間で行う点呼方法です。
業務前点呼、中間点呼、業務後点呼のいずれにおいても実施可能で、Gマーク認定がなくても実施できます。1営業日のうち連続して実施できる時間にも制限がありません。なお、使用する機器やシステム、点呼を行う施設や環境、遵守事項に適合する必要があります。
▼詳しくは下記の記事で解説していますので、参考にしてください。
2023年1月より「業務後自動点呼」が運用開始
業務後自動点呼(乗務後自動点呼)とは、従来の対面点呼と同様の確実性を保ちながら、ドライバーが乗務を終えた後に行われる点呼を自動点呼機器に代替する点呼方法です。業務後自動点呼は2023年1月より運用開始されました。
国土交通省の認可を受けた自動点呼機器を利用する必要があるものの、IT点呼や遠隔点呼で求められていた点呼執行者の代わりをAIやロボット、ICT機器が担うため、一部の業務負担を軽減できます。
ただし、乗務前や中間点呼には使用できず、あくまでも乗務後に限定されます。営業所または車庫において実施される点呼であるため、遠隔地において乗務を終了する際には、業務後自動点呼の適用は認められません。
導入された背景と導入の条件について分かりやすく紹介します。
導入された背景
近年、運送業界など事業用自動車を利用する事業所では、労働環境の改善や人手不足の解決が急務とされています。ICTを活用した高度な点呼機器の利用ができれば、点呼の確実性を担保しつつ点呼にかかる労働時間を減らすことが期待されています。
業務前点呼と業務後点呼では、下記の通り確認項目が異なります。
| 業務前点呼の確認項目 | 業務後点呼の確認項目 |
|---|---|
| ・酒気帯びの有無 ・健康状態 ・日常点検結果 ・運転特性の注意 ・安全確保のための必要な指示 ・乗務可否の判断 | ・酒気帯びの有無 ・道路交通状況 ・苦情等 ・異常の有無 ・勤務内容 |
総合的に運行の可否を判断する必要がある業務前点呼に比べ、業務後点呼は実施項目が少なく導入が容易です。そのため、業務後点呼から従来の対面点呼に代わり、点呼機器を用いた自動点呼の導入を進める運びとなりました。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
業務後自動点呼の導入の条件
業務後自動点呼を導入するには、以下の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 機器システムの機能 | 国土交通省の基準に適合した機器 |
| 施設環境の要件 | 適切な監視とセキュリティの確保、不正利用を防ぐ設計、故障の際に点呼代行者が常に対応できる体制など |
| 実施時の遵守事項 | 点呼機器の使用方法の教育、定期的な運用状況の報告など |
非常時には点呼執行者の対応が必要であるため、立ち会いが不要だとしても体制の構築は求められます。また、遠隔地での点呼には利用できない点にも留意してください。
※出典:“遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報”.国土交通省.(参照 2024-7-25)
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
※出典:“乗務後自動点呼実施要領”.国土交通省.2022-12-20(参照 2024-7-25)
業務後自動点呼を導入するメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 運行管理者の業務効率の向上 | なりすましの可能性 |
| 運転手の利便性向上 | 運用開始までの準備 |
| 正確性の確保 | 導入費用 |
業務後自動点呼のメリットとデメリットについて1つずつ分かりやすく紹介します。
業務後自動点呼を導入するメリット
運行管理者の業務効率の向上
対面点呼にかかる時間や手間が軽減され、運行管理者はより効率的に業務を進められます。本来の役割である安全運行の確保や教育などに注力できるようになり、全体的な運行管理の質が向上し、運転手の安全を確保できるようになります。
運転手の利便性向上
業務後自動点呼によって時間や場所の制約を受けずに点呼を完了できます。また、運転手は自分の都合に合わせて点呼の結果や指示事項をシステム上で確認可能です。
正確性の確保
アルコールチェックや健康状態の確認などが自動的に行われ、デジタルデータとして記録できることでヒューマンエラーが排除できます。また、蓄積された点呼データを分析することで、運転手の健康管理や安全運転指導の改善への活用も可能です。
業務後自動点呼を導入するデメリット
なりすましの可能性
対面点呼では、運行管理者が運転手の顔を直接確認することで本人確認を行っていましたが、自動点呼ではカメラを通した確認となるため、他人が運転手になりすまして点呼を受ける可能性が完全には排除できません。
運用開始までの準備
機器やシステムの選定と導入を行う必要や、国土交通省への申請手続きが発生します。運用開始前には、運転手や運行管理者への教育も必要です。
導入費用
初期費用と運用費用がかかります。特に、顔認証などの高度な機能を持つ機器を導入する場合は、費用が高額になる傾向にあります。機器やシステムの保守費用や、通信費などの運用費用も別途必要です。
業務後自動点呼の3つの要件
業務後自動点呼は基本的に機器で行いますが、対面点呼と同様に、責任は事業者や運行管理者が負うことになります。体制を整え、適切に運用していく必要があります。
業務後自動点呼の要件は以下の3点です。
- 機器・システムが満たすべき要件
- 施設環境要件
- 運用上の遵守事項
それぞれについて分かりやすく解説します。
機器・システムが満たすべき要件
機器・システムが満たすべき要件は、次の4つの項目に分類されます。
- 業務後自動点呼に関する基本要件
- なりすましの防止
- 運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知
- 点呼結果、機器故障時の記録
業務後自動点呼に関する基本要件
業務後自動点呼に関する基本要件は、以下の4点です。
- アルコールチェックの結果と、チェック中の写真・動画を自動で保存できる。
- 運転手の報告内容を電子的に記録、または対話形式で報告を受けることができる。
- 運行管理者からの指示を各運転手に伝えることができる。
- 運行管理者が各運転手の点呼スケジュールと結果を確認できる。
業務後自動点呼を行う機器・システムが運行管理者の行う業務(業務にあたって必要となる情報の伝達や共有)を代替できる機能を備えている必要があります。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
なりすましの防止
業務後自動点呼のなりすまし防止の要件は、以下の2点です。
- 点呼時には、あらかじめ登録された運転手だけが応答できるよう、個人を正確に識別する生体認証システム(顔、静脈、虹彩などの認証方法)を使うこと。
- アルコール検知時には、点呼対象の運転手のみが検査を受けられるよう、上記同様の生体認証を使うこと。
点呼を受けている人が誰かを特定する要件です。搭載されている生体認証機能は、確実に個人を識別できる必要があります。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知
運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知に関する要件は、以下の場合に点呼を保留にし、運行管理者などへ警告や通知を出すことができる必要があります。
- 酒気を帯びていると判断した場合。
- 予定時刻が過ぎても点呼されない場合。
- 点呼項目がすべて実施されない場合。
機器の故障が発生した際には、故障内容を表示し運行管理者に通知が届き、故障が直るまで点呼ができないようにする機能が必要です。運行管理者は警報が発生した運転手とのやり取りや、代わりの乗務員の確保のため、常に対応できる状態であることが求められます。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
点呼結果、機器故障時の記録
点呼結果、機器故障時の記録の要件は、以下の4点です。
- 各運転手の点呼記録を1年間保存できること。
- 機器が故障した場合は、その日付、時刻、故障内容を記録できること。
- 記録された結果や故障内容は、修正ができないこと。修正された場合でも、修正前の記録を消去できないこと。
- 記録された結果や故障内容は、CSV形式などで出力可能であること。
運転手の点呼結果はすべて電子的に記録し、1年間保管しなければなりません。記録が修正できないことや、修正された場合でも修正前の記録を消去できないことが必要です。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
施設環境要件
業務後自動点呼での施設環境要件は、以下の1点です。
- 運転手が勤務終了後の自動点呼を行う様子を、運行管理者などがいつでも確認できるように、防犯カメラなどを適切な場所に設置すること。
なりすましやその他の不正行為、勤務終了後の点呼が指定された場所以外で行われることを防止するために設けられています。なお、2024年4月に監視カメラの要件は改定され、クラウド型のドライブレコーダー、スマートフォンなどの使用も可能です。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
※出典:“遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント”.全日本トラック協会.2024-3(参照 2024-7-25)
運用上の遵守事項
業務後自動点呼における運用上の遵守事項は、次の3つの項目に分けられます。
- 事業者、運行管理者等に係る遵守事項
- 非常時の対応
- 個人情報管理に係る事項
事業者、運行管理者等に係る遵守事項
事業者、運行管理者等に係る遵守事項は、以下の8点です。
- 自動点呼に関する必要事項を事前に運行管理規程に記載し、運転手や運行管理者に伝えること。
- 機器がいつでも正常に動作するよう、適切な使用、管理、保守を行い、定期的に故障がないかをチェックすること。
- 機器が所定の場所から持ち出されないように、適切な措置を講じること。
- 自動点呼の運用における責任は事業者と運行管理者にあるため、関係者が機器を正しく使えるように教育体制を整えること。
- 運行管理者は、運転手が自動点呼を予定通りに実施しているかを適切にチェックし、点呼の漏れがないようにすること。
- 事業者は、運転手が持ち物を確実に返却したことを確認できるように体制を整えること。
事業者や運行管理者は、運転手を含むすべての利用者が機器を適切に使用できる環境を整備する必要があります。機器による点呼を実施する場合でも、対面点呼と同様、事業者または運行管理者がその責任を負わなければなりません。自動点呼機器には個人情報が含まれるため、第三者に利用されないような仕組みづくりが求められます。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
※出典:“乗務後自動点呼実施要領”.国土交通省.2022-12-20(参照 2024-7-25)
非常時の対応
非常時の対応における要件は、以下の3点です。
- 酒気を帯びが検知されたら、運行管理者がすぐに対応できるように準備しておくこと。
- 緊急の報告が必要な場合、運転手が運行管理者に報告できる体制を整えておくこと。
- 機器が故障した場合は、運転管理者が点呼を行うこと。
自動点呼に対応できない場合は、運行管理者による対面点呼が必要となるため、安定して運用できるまでは従来の方法と並行すると安全です。業務後自動点呼に切り替えた後でも非常事態に備え、体制を整えておくことが重要です。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
個人情報管理に係る事項
個人情報管理に係る事項は、以下の1点です。
- 運転手の認証に必要な生体情報を含む個人情報を扱う際は、事業者が対象者の同意を得ること。
指紋や虹彩などは個人情報となるため、目的以外で利用せず、安全に管理できる体制を整えることが大切です。
※出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”.国土交通省.2022-3-23(参照 2024-7-25)
自動点呼を導入する方法
自動点呼の導入には、「自動点呼機器の用意」と「運輸支局長への申請書の提出」が必要です。
自動点呼機器を用意する
国土交通省の認定を受けた「点呼支援機器」を用意する必要があります。国土交通省のホームページから確認できます。自社社の運行形態やニーズに合ったものを選びましょう。
運輸支局長へ事前に届出書を提出する
点呼支援機器を用意したら、自動点呼の実施予定日の10日前までに運輸支局長へ所定の届出書を提出します。使用する機器の詳細や点呼の手順、緊急時の対応方法などを記載します。届出書は国土交通省のホームページより確認しましょう。
自動点呼の導入に利用できる助成金
全日本トラック協会が支援する「自動点呼機器導入促進助成事業 」と「安全装置等導入促進助成事業」の2つが挙げられます。
自動点呼機器導入促進助成事業
全日本トラック協会は、安全性の向上や人手不足の解消などを目的として、会員事業者が自動点呼機器を導入する場合、費用の一部を助成する事業を実施しています。助成対象となるのは、2024年4月1日以降に契約または利用を開始した自動点呼機器です。
| 助成対象 | 各都道府県トラック協会の会員事業者で、中小企業者を対象※中小事業者とは、中小企業基本法による中小企業者 ・資本金の額または出資の総額が、3億円以下の会社 または ・常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 助成金額 | 対象となる自動点呼機器の導入費用(周辺機器、セットアップ費用及び契約期間中のサービス利用料を含む)(上限10万円)Gマーク事業所を有する事業者は2台分(上限20万円) |
| 申請方法 | 各都道府県のトラック協会ホームページより申請書をダウンロード、業務後自動点呼の実施に係る届出書などを添付し申請する |
※出典:“令和6年度 自動点呼機器導入促進助成事業について”.全日本トラック協会.2024-3(参照 2024-7-25)
安全装置等導入促進助成事業
全日本トラック協会は事業用トラックの交通事故ゼロを目指し、導入機器に対する費用を助成する事業を実施しています。その中に「遠隔地での点呼に使用する携帯型アルコール検知器」も含まれています。
| 助成対象 | 被測定者の意思によらず自動で測定結果を営業所設置の端末に送信できる機器、Gマーク認定事業所が導入するものに限る |
| 助成金額 | 対象装置ごとに機器取得価格の1/2、上限2万円 |
| 申請方法 | 各都道府県のトラック協会ホームページより申請書をダウンロード、Gマーク認定証の写しなどを添付し申請する |
出典:“令和6年度安全装置等導入促進助成事業について”.全日本トラック協会(参照 2024-7-25)
自動点呼を導入するならSafieのクラウドカメラ
Safie(セーフィー)のクラウドカメラは、東海電子の点呼システム「e点呼PRO」とシステム連携が可能、業務後自動点呼の導入をスムーズに実現することができます。Safieのクラウドカメラであれば、業務後自動点呼の機器要件を満たしており、かつ低価格で手軽に始めることが可能です。
点呼システム「e点呼PRO」とのシステム連携
東海電子が提供する点呼システム「e点呼PRO」との連携で、遠隔地からの点呼と点呼記録の一元管理を可能にしています。点呼の様子はクラウド上に録画され、その記録は自動的に「e点呼PRO」に反映されます。さらに、2024年4月から義務化された貸切バス運転士の乗務前後における「デジタル点呼記録」にも対応しています。
業務後自動点呼に最適なSafieのクラウドカメラ
Safieのクラウドカメラは、HD画質×30fpsなのでキレイでなめらか。業務後自動点呼の要件基準を満たしています。録画した映像データはクラウドに保存されるため、PCやスマートフォンから、いつでも確認できます。
使いやすいUIは、複数のカメラの映像を一覧表示したり、特定のカメラをソートして表示したりすることが可能で、効率よく映像を確認することができます。
【導入事例】Safieで点呼業務時間を短縮
総合物流企業A社では、物流の2024年問題を解決するため、運行管理者の稼働時間削減と業務効率化が求められていました。対面点呼業務に多くの時間と工数がかかり、残業も発生したが、Safieのクラウドカメラの導入により状況が一変。直感的な操作で点呼状況をすぐに確認でき、管理工数が大幅に削減されました。
導入後は、平日1日1時間、土曜日は4時間の業務時間を短縮。遠隔から現場状況を把握し、事故やトラブルのエビデンスにも活用できる、と効果を実感しています。
まとめ
自動点呼は、運転手の安全管理を強化し、運行管理業務を効率化できる点呼方法です。適切な施設や環境を整え、法令を遵守した運用を心がけることで、事故防止や業務改善に繋がります。また、助成金制度を活用することで、導入費用を抑えることも可能です。
Safieのクラウドカメラなら、点呼システムとのシステム連携や、高画質な映像で、自動点呼の導入負担を軽減しながら、効果的な運用が可能です。業務後自動点呼をご検討の方は、ぜひお問い合わせください。
- いつでもどこでも映像が見られるクラウドカメラ
- スマホやパソコンから店舗・現場を見える化!
本記事の監修者
行政書士法人シグマ 代表 行政書士
阪本 浩毅(さかもと ひろき)
都内の司法書士法人・行政書士法人にて企業法務に従事。行政書士として独立後は、運輸業専門として数多くの一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業に関する許認可法務に関与。現在は行政書士法人の経営を行いながら、運輸業の許認可法務の実務家として活動中。
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。