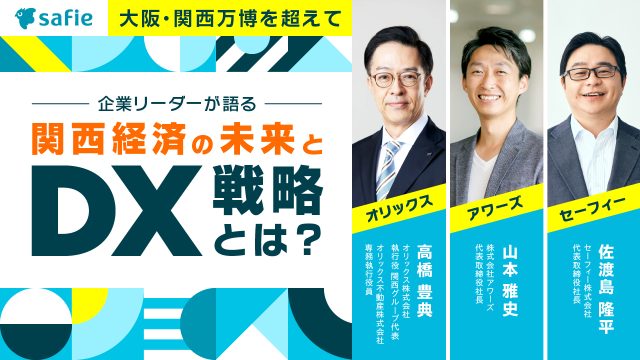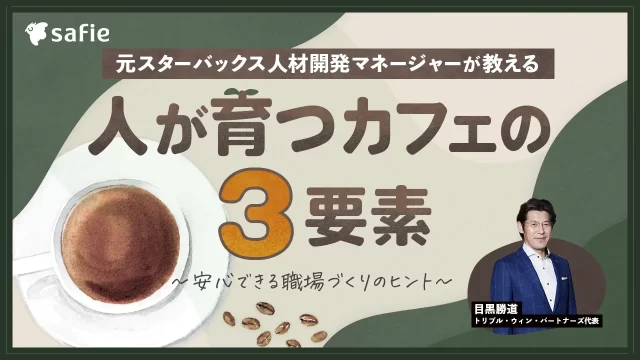2021年の介護報酬改定により、介護事業所におけるBCP(事業継続計画)の策定が義務化されました。3年間の経過措置期間を経て、2024年4月からはすべての介護事務所でBCP策定が完全義務化されています。策定していない場合は、介護報酬の減算や法的責任を問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。
本記事では、BCPとは何かを説明するとともに、策定すべき項目や策定のためのステップなどについて解説します。
目次
介護事業所におけるBCP(事業継続計画)とは?

「BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)」は、組織が予期せぬ災害や危機的状況に直面した際に、事業活動を継続し、最小限の影響で復旧するための対応計画です。BCPは組織の持続性を確保するために事前に準備され、災害発生時に迅速に実行される必要があります。
介護事業所は、サービスの停止が利用者の健康や生活の質に大きな影響を与え、場合によっては安全にも関わるため、継続的なサービス提供が求められる事業です。そのため、2021年4月から介護事業者は「BCP(事業継続計画)」の策定が義務化されました。
義務化には3年の経過措置が設けられていましたが、2024年4月からは全ての施設・事業所においてBCPの策定が必要とされています。
BCPの目的と意義
BCPの目的は、緊急事態に備えて事前に対策を講じ、発生時の迅速な対応によって事業の早期復旧を実現することです。計画がないと対応が後手に回り、復旧の遅れが利用者離れや事業存続の危機につながる可能性があります。
特に介護分野では、すべての利用者の安全と尊厳を守るための配慮が不可欠です。避難支援や医療機器の継続使用、感染症対策など、介護サービスの特性に応じた対応を事前に計画しておくことが重要です。非常時でも1人ひとりに合わせた継続的なケアを提供できるように整えておくことが、介護事業所のBCPにとって大切なことなのです。
介護事業者が対応する主なリスク
内閣府の「事業継続ガイドライン」によれば、BCPは以下であると定義されています。
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。
引用元:“事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(平成25年8月改定)P3”. 内閣府(防災担当). 2013-08(参照 2025-05-19)
介護事業者においても、施設の火災、大規模停電、食中毒など様々なリスクに対応する必要がありますが、特に厚生労働省が具体的なガイドラインを整備し、対応が求められている分野が以下の2つです。
自然災害の発生
地震・津波・洪水・土砂崩れなどの災害が発生した場合、介護サービスの継続は困難な状況に直面します。特に建物・設備の損壊、インフラの停止、人手不足などの複合的な問題に対応する準備が必要です。
感染症のまん延
新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザなどの感染症が広まった場合でも、介護事業者は感染防止対策を徹底し、サービスの持続的な提供が求められます。感染症の流行が長期化すると、職員の感染など、様々な側面から事業継続が脅かされるリスクがあります。
BCPとBCMの違い
BCPと関連する概念として、BCM(Business Continuity Management)があります。BCMは事業継続を確保するための包括的な管理アプローチで、緊急時の対応だけでなく、予算・資源の確保や従業員教育・訓練など、平常時からの管理活動を含みます。BCPはBCMの一部であり、緊急時における具体的な継続計画です。
防災計画との違い
防災計画は、災害発生時の利用者・従業員の安全確保と建物・資産の被害を最小限に抑えることを目的としています。
一方BCPは、安全確保に加え、重要な業務の維持と復旧に焦点を当てています。両者は密接に関係しながらも、BCPはより広範囲で、感染症拡大などの様々な事業中断要因への対策を含みます。また、避難計画、事業の継続性、地域貢献などの総合的な視点も重要です。
引用元:“介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン”. 厚生労働省 老健局. 2020-12-01(参照 2025-05-19)
BCP策定時に盛り込む重要項目
BCPには以下の項目を盛り込む必要があります。
自然災害対策の具体的項目
自然災害対策では、「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて準備します(※1)。
事前の対策として特に重要なのは、以下2点です。
- 設備・機器・什器(じゅうき:備品や家具など)の耐震固定
- インフラが停止した場合の対応
被災時の対策では、人命の安全確保や事業復旧に向けたルールの策定、初動対応の手順を具体的に検討します。具体的には、利用者・職員の安全確保・安否確認、建物・設備の被害点検、そして職員の参集方法などを定めておきます。
感染症対策の具体的項目
感染症対策に関するBCP策定では、次の項目について整理します(※2)。
- 情報共有と役割分担、適切な判断ができる体制の構築
- 感染者が発生した場合の対応手順(隔離、消毒など)
- 職員不足時の人員確保(応援体制、シフト調整など)
- 少人数体制で業務を遂行するための優先順位の整理
- 計画の周知、研修・訓練の実施
感染者や感染の疑いがある人が確認された場合に、迅速に対応するためには、緊急時の体制構築が重要です。そのために普段からシミュレーションを実施し、職員不足時の人員確保策や業務の優先順位についても、あらかじめ整理しておきましょう。
BCPは策定するだけでは不十分で、実際の緊急時に機能する実践的な内容にすることが重要です。そのためには、関係者への十分な周知や定期的な研修・訓練が欠かせません。
BCPを策定しないとどうなる?
BCP策定は2024年4月から義務化されており、未策定の場合には次のようなリスクがあります。
介護報酬が減算される
厚生労働省は令和6年度の介護報酬改定において、感染症または災害、あるいはその両方に対応したBCPを策定していない介護事業所に対して、基本報酬の減算を行う旨の規定を新設しています(※3)。
施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他のサービスでは100分の1に相当する単位数が減算されます。これは事業所の収益に直接影響するため、早急な対応が求められます。
安全配慮義務が問われる
災害や感染症発生時には、利用者と職員の安全確保が事業者に求められます。BCPがない状態では適切な対応が困難となり、結果として安全確保が十分にできない可能性があります。
また、BCPを策定していても、その内容が職員間で共有されておらず実際に運用できない状態では、緊急時に十分な効果を発揮できません。策定だけでなく、実効性のある運用体制の構築も重要です。
時間や人材の制約でBCP策定が難しい場合は、厚生労働省が提供する解説動画を活用すると良いでしょう。BCPの基本的な考え方、策定のプロセスの理解に役立ちます。
BCP策定によって得られる5つのメリット

介護事業者がBCPを策定すると、非常事態時に適切な対応ができるだけでなく、次のようなメリットが期待できます。
事業継続強化計画の認定で税制優遇が受けられる
BCPを策定した後、その内容を踏まえて「事業継続力強化計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受けると、防災・減災設備投資に税制優遇が適用されます。2027年3月31日までに認定を受け、認定から1年以内に計画記載の設備を導入した事業者は、特別償却16%の優遇措置が受けられます。
詳細は「税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置)について」をご確認ください。
金融支援が受けられる
日本政策金融公庫では、BCPに基づく防災施設整備のための融資制度「BCP資金」を提供しています。自社で策定したBCPや認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、防災施設の整備を行う中小企業が対象です。融資限度額は7億2千万円(直接貸付)で、設備資金は最長20年、運転資金は最長7年の返済期間となっています。詳細は「BCP資金」をご確認ください。
災害対策が強化される
BCPを策定することで、災害発生時の初動対応や事業復旧の手順が明確になり、被害の最小化につながります。人命保護はもちろん、設備・情報資産の保全、業務の早期復旧など、災害に対する総合的な備えが強化されるのもメリットの1つです。
特定接種の登録要件の一部を満たすことができる
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録事業者となるための要件の一つとして、BCPの策定が含まれています。
ただし、政府のQ&Aによれば「ワクチンはあくまで業務継続のための支援ツールの1つ」であり、「登録されたことを以て特定接種を受けられるわけではない」とされています。BCPを策定する際は、新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針も含めておくと、将来的に特定接種の登録要件の一部を満たすことができますが、実際の特定接種の実施は発生時の状況により決定されます。
詳細は特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&Aもご確認ください。
事業所の価値の向上につながる
BCPを策定・運用することで、利用者やその家族から「危機的な状況でも対応できる事業者」として評価される可能性があります。また、職員にとっても、緊急時の対応手順が明確になることで安心して業務に取り組める環境が生まれます。こうした信頼性の向上は、長期的に見れば事業所の価値を高める要素となるでしょう。
BCP策定の進め方

介護事業所のBCPを効果的に策定するには、現状の分析から始め、段階的に必要な要素を整理していくことが重要です。ここでは、BCPの策定準備から具体的な作成ステップまで、実践的なプロセスをご紹介します。
策定前の準備|現状診断に役立つツールとひな形
現在の事業所のBCP対応レベルを確認してみましょう。中小企業庁が提供している「BCP取組状況チェック」を活用すると、簡単に自己診断できます。介護事業所の多くは中小企業に該当するため、このツールが参考になります。「はい」に該当する項目数と診断結果を確認し、課題を把握しましょう。
また、厚生労働省が提供するBCP策定用のひな形を活用すると、効率的に文書化を進められます。ひな形は大きく分けて感染症対策用と自然災害対策用の2種類があり、さらに事業形態に応じた複数の種類が用意されています。
- 感染症対策用:「入所系」「通所系」「訪問系」の3種類
- 自然災害対策用:共通様式とサービス固有様式
これらから事業所の形態に最適なひな形を選んで活用しましょう。また、先に紹介したように厚生労働省のウェブサイトでは策定方法を解説する動画や、作成したBCPを活用するための机上訓練の動画も公開されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
▶厚生労働省のひな形のページはこちら
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
具体的な策定の6つのステップ
以下の6つのステップを順番に進めていくことで、体系的にBCPを完成させることができます。
1. BCP策定の責任者を決める
責任者を中心に、部門横断的なBCP推進メンバーを選定します。ひな形の「様式1」(推進体制の構成メンバー)を活用し、推進体制を明確化しましょう。
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
2. 連絡先を整理する
緊急時に連絡が必要な相手先をリスト化します。医療機関や自治体だけでなく、建物・エレベーター等の設備関連、水道・電気などのインフラ関連の連絡先、職員の緊急連絡網も整備しておきましょう。ひな形の「様式2」(施設外・事業所外連絡リスト)と「様式5」([部署ごと]職員緊急連絡網)が活用できます。
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
3. 備蓄品を整理する
必要な備蓄品をリストアップします。ひな形の「様式6」(備蓄品リスト)に基本的な備蓄品例が記載されているので、施設の状況に合わせて更新しましょう。
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
4. 優先業務を特定する
災害時などに継続すべき業務の優先順位を決めます。さらに、職員の出勤率に応じて、継続必須の業務や一時休止が可能な業務を分類しておきましょう。ひな形の「様式7」(業務分類[優先業務の選定])を活用すると整理しやすくなります。
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
5. 利用者の安否確認計画を作成する
利用者の方々の状況を把握し、医療的ケアが必要な方、避難に特別な配慮が必要な方など、緊急時に迅速な対応が求められる方を確認します。これらの情報を整理したリストを作成し、災害発生時の支援体制を事前に検討しておきましょう。
すべての利用者の安全を確保するために、効率的な情報共有の仕組みも併せて整備することが大切です。自然災害ひな形(共通)の「様式9」(災害時利用者一覧表[安否確認優先順位])が参考になります。
引用元:“介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-01(参照 2025-05-19)
6. 重要業務の復旧目標を設定する
重要な設備や特定の医療機器が停止した場合、いつまでに復旧させる必要があるかを検討し、事業所の状況に合わせた復旧目標を設定します。たとえば「医療機器の稼働を維持する」「最低限のケアサービスを〇時間以内に再開する」といった具体的な目標を立てます。
参考として、東日本大震災の経験から報告されているインフラの復旧目安は以下の通りです(※4)。これらの情報も考慮し、現実的な復旧目標を設定しましょう。
- 震度7の場合の完全復旧時間:電力は約1週間、水道は約3週間、ガスは約5週間
- 震度7の場合の50%までの復旧時間:電力は約3日、水道は1週間、ガスは3週間
震度6以下の場合、上記の期間よりも短縮されると想定されます。
上記の6つのステップに沿って準備を進めることで、実効性のあるBCPを策定することができます。
介護事業所におけるBCP策定のポイント・注意点
介護事業所がBCPを策定する際は、実効性を高めるため、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、BCPを実際の対応に活かすための注意点を解説します。
明確な役割分担や情報共有体制の構築
BCP策定において、災害や感染者発生時の役割分担を明確にしておくことが重要です。「誰が」「何を」するかをあらかじめ定めておくことで、混乱を最小限に抑えられます。
また、関係者との連絡体制も重要です。利用者とその家族、行政機関、ほかの介護事業所などの連絡先リストを作成し、定期的に更新することが効果的です。
職員不足への対応策を検討する
災害発生時や感染症の流行時には、職員の出勤が難しくなることがあります。このような状況に備えて、事前に対応策を検討しておくことが重要です。具体的には次のような対策が考えられます。
- 同一法人内の他事業所との応援体制構築
- 地域の他法人との協力関係構築
- 元職員や退職予定者への協力依頼
また、職員数の減少を想定したシフトの調整案も、複数パターン準備しておくと安心です。
業務の優先順位を設定する
限られた職員でサービスを継続するためには、業務の優先順位を設定することが必要です。具体的には、以下のように業務を分類します。
- 継続が必須の業務(利用者の生命・健康に直結するケア等)
- 緊急時に発生する追加業務(情報収集、対外連絡等)
- 縮小や一時中断が可能な業務
たとえば、医療ケアや食事介助は最優先業務となる一方、一部の事務作業やレクリエーションは状況に応じて調整することが考えられます。
必要物資の備蓄と管理体制の整備
緊急時に必要な物資は、平時から計画的に準備しておくことが大切です。介護事業所では一般的な防災備品に加え、次のような物資の確保が望ましいとされています。
- 飲料水・非常食
- 衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)
- 避難用具(搬送用ベルト、簡易担架等)
- 医療関連用品(常備薬、簡易ベッド等)
また、備蓄品の管理担当者を決め、使用期限の確認など、管理体制を整備することも重要です。
複数の連絡手段を確保する
災害時には通信インフラが使えなくなることがあります。そのため、複数の連絡手段を用意しておくことが重要です。たとえば、携帯電話やスマートフォンだけでなく、固定電話、SNS、メールなど、複数の手段を確保しておきましょう。
定期的な研修・訓練の実施
BCPを緊急時に活かすためには、普段から研修や訓練を行うことが大切です。訓練には、机上訓練(シミュレーション)と実地訓練の両方を行うことが効果的です。厚生労働省が公開している机上訓練の研修動画も参考になりますので、職員教育に活用してください。
▶机上訓練の研修動画はこちら
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
BCP対策をサポートするデジタルツール

BCPの策定と実行においては、適切なツールの活用が効果的です。ここでは、介護事業所のBCP対策に役立つデジタルツールの一例として、クラウドカメラについてご紹介します。
クラウドカメラは、インターネットを通じて映像をクラウド上に保存できるのが特徴です。平常時の見守りや記録としての活用に加え、BCPの補完ツールとしても役立つ可能性があります。たとえば以下が挙げられます。
| 感染症対策における活用 | 感染症流行時に職員の接触機会を減らしながら、遠隔からの利用者の方々の見守りが可能 |
| 事業記録の保全 | 映像データがクラウドに保存されるため、施設内の記録媒体が被災しても情報が失われにくい |
| 限られた人員でのケア支援 | 人員不足時でも、常時確認が必要な場所の状況を効率的にチェックできる |
ただし、人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。
▼防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
BCP策定で安心・安全な介護サービスの提供を

介護事業所におけるBCPは、自然災害や感染症発生時に施設の利用者とそのご家族、そして職員の安全を守るための重要な指針です。実際の緊急時に機能する実践的な内容にするには、感染症と自然災害の両方への対策を盛り込み、役割分担や業務の優先順位を明確にしましょう。また、定期的な研修・訓練を通じて実効性を高めておくことも大切なポイントです。
監修者情報:行政書士 中司勇士
作業療法士として医療・介護現場でリハビリを行いながら研究活動にも注力。報酬改定時の院内システムの構築にも携わり、改正点のスタッフへの周知を図る。現在は行政書士として行政と医療・介護現場の架け橋として各種助言やサポートを行っている。
・ホームページURL:なかつか行政書士事務所
- 介護業界向けクラウドカメラ活用ガイド
- 介護施設におけるクラウドカメラの活用方法をご紹介しています。
※1 出典:“介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラインP7”. 厚生労働省 老健局. 2024-03(参照 2025-05-19)
※2 出典:“介護サービス事業者における業務継続ガイドライン(新型コロナウイルス感染症対応版)P6”. 厚生労働省. 2023-05-08(参照 2025-05-19)
※3 出典:“令和6年度介護報酬改定における改定事項について”. 厚生労働省 老健局. 2021-03-31(参照 2025-05-19)
※4 出典:“業務継続計画(BCP)自然災害編(介護サービス類型:共通)P20”. 厚生労働省 老健局. 2021-11-11(参照 2025-05-19)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。