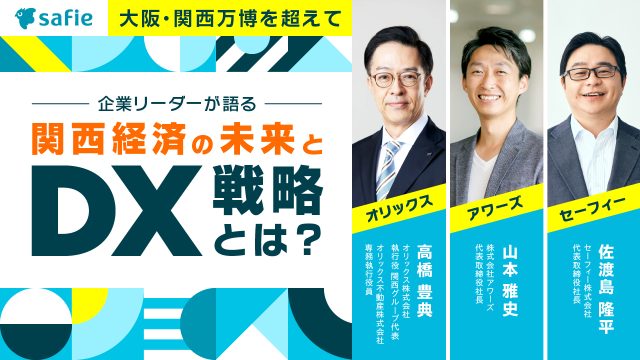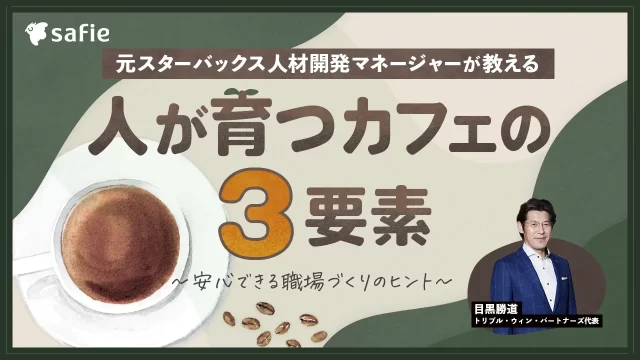「業務前自動点呼」は、2025年4月30日に告示が改正され、本記事執筆時点(2025年7月)では、業務前自動点呼に使用する機器の認定手続きが国土交通省内で行われています。運用開始は機器認定手続きが完了し、通達が発令されてからになると考えられます。
運送事業者において、これまでは業務終了後の点呼は機器による自動化が認められていましたが、業務開始前の点呼は自動化の制度が整備されていませんでした。
本記事では、業務前自動点呼が開始される背景や、制度開始によって期待される効果、懸念点についてわかりやすく解説します。
目次
業務前自動点呼とは

業務前自動点呼とは、運送事業者が運転者(ドライバー)に対して運転業務開始前に行う点呼を、国土交通省が認定した業務前自動点呼機器を用いて自動で行うことです。
運送事業者には、ドライバーや運送の安全を保つために、業務開始前と終了後の点呼が義務付けられています。
点呼は原則的に、国家資格を保有する運行管理者や運行管理補助者、貨物軽自動車安全管理者(以下、運行管理者等)と対面により実施しなければなりません。業務前自動点呼は、業務前の点呼を対面以外で実施する方法の1つです。
業務前自動点呼については、2023年度から2025年にかけて、制度化に向けた先行実施が行われてきました(※1)。その結果の分析・考察により要件がまとめられ、2025年4月30日に「対面による点呼と同等の効果を有する方法」を定めた国土交通省の告示が改正されました。
業務前自動点呼を実施するためには、事前に管轄の運輸支局長等への届出が必要です。要件を満たした機器・システムを導入し、施設や環境の要件も満たさなければなりません(※2)。そのうえで、定められた遵守事項に沿って運用する必要があります。要件の概要は告示に記載されていますが、詳細についてはさらなる情報が公開されると考えられます。
業務前の点呼とは
業務前の点呼では、主に次の点を確認します(※2)。
- 健康状態の確認
- ドライバーの本人確認
- 酒気帯びの確認
- 車両の安全性の確認
- 運行管理者による指示の伝達 等
業務前の点呼では、ドライバーが安全な運行が可能であるかを判断しなければなりません。そのため、業務後の点呼に比べると重要度が高く、制度化にあたっては慎重な議論と長期にわたる検討が重ねられてきました。
業務後自動点呼との違い
業務後の点呼を自動化する「業務後自動点呼」は、業務前自動点呼に先駆けて2023年に制度化されました。運転業務の終了後に機器を用いて自動点呼をすることを、対面の点呼と同等の効果を有するものとして認めた制度です。
業務後の点呼では、主に次の点を確認します(※3)。
- ドライバーの本人確認
- 酒気帯びの確認
- 車両・道路・運行状況報告
- 積荷状況・苦情等確認 等
業務後自動点呼を導入していなくても、業務前自動点呼を開始することは可能です。点呼そのものは義務ですが、手段は対面・遠隔・自動等さまざまであり、自社に適したものを選べば問題はありません。業務前は対面点呼、業務後は自動点呼という形式でも問題なく、その逆もあり得ます。
なお、業務後自動点呼も業務前自動点呼と同様に、実施にあたっては告示で定められた要件を満たす必要があります。具体的な手続き等については、各運輸支局等の最新の情報をご確認ください。
業務前自動点呼の制度化の背景・経緯
業務前自動点呼が制度化される背景には、点呼をより効率的に進める流れや運送業界における「2024年問題」等が挙げられます。それぞれの経緯について、以下で詳しくみていきましょう。
点呼の遠隔化・自動化の流れ
もともと点呼は、運行管理者等と対面して行うことが原則でした。業務前と業務後は必ず行いますが、いずれの点呼も対面でできない場合は、業務中に点呼を実施(中間点呼)しなければなりませんでした(※4)。
しかし近年は、対面以外の方法で点呼を実施することも選択できるようになっています。2023年には、遠隔で運行管理者と点呼ができる「遠隔点呼」や、業務後の点呼の全部または一部を自動化できる「業務後自動点呼」が認められました。
こうした流れの中で、業務前自動点呼も2025年4月30日に告示が改正され、運用に向けての準備が進められています。
2024年問題の解消に向けた動き
業務前自動点呼が制度化される背景には、物流業界における「2024年問題」への対応という側面もあります。
2024年4月に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(※5)」が改正され、タクシーやトラック、バス等のドライバーの労働時間が規制されました。一人ひとりのドライバーが運転できる時間が短縮され、運送業界の人材不足や高齢化も相まって、輸送力の大幅な低下が懸念されています。
こうした「2024年問題」の解消に向けてはさまざまな対策が講じられており、業務前自動点呼もその1つです。
業務前自動点呼の導入意義・期待される効果

国土交通省が主導する自動点呼の導入についての検討会「運行管理高度化ワーキンググループ」が公表した「業務前自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて」によると、業務前自動点呼を導入する目的や意義としては、次のものが挙げられています(※2)。
- 点呼執行者の深夜、早朝、休日の労働時間削減(90.6%)
- 点呼の確実性向上(78.8%)
- 健康起因の事故防止(73.0%)
- 業務効率化による経費削減(69.3%)等
点呼に立ち会う人員の労働時間の削減は、とくに多くの事業者が期待する事項です。運送業の運行は深夜や早朝に開始されることも多くあります。運行管理者等が点呼のためだけに出勤することも珍しくありません。業務前自動点呼を導入することで、運行管理者等がいなくても点呼ができるため、運行管理者等の拘束時間の削減が可能です。
このほか、ヒューマンエラーを減らして点呼を確実に実施することや、ドライバーの健康状態に基準値を設けて無理な運転を避けることも、期待されている効果です。運行管理者等だけでなく、ドライバーにとっても効率的な点呼の実施が期待されます。
業務前自動点呼の運用における懸念点
さまざまな効果が期待される業務前自動点呼ですが、次の懸念点もあります。
- 点呼がスムーズに完了しない場合がある
- なりすましへの対策が必要である
それぞれの内容と対策について、以下で詳しく紹介します。
点呼がスムーズに完了しない場合がある
「業務前自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて」によると、業務前自動点呼を先行的に実施する中で、業務前自動点呼を中断・中止する事業者もいたことがわかりました(※2)。具体的には、次のようなことが発生しました。
- 睡眠時間を誤って入力した
- 体温が平常値からの許容範囲を超えた
- 血圧が平常値からの許容範囲を超えた
- マウスウォッシュやうがい薬によってアルコール呼気濃度が高く計測された
- 自動点呼機器やインターネット等の不具合により自動点呼ができなかった
- 自動点呼機器への誤入力や不備により自動点呼ができなかった
これらの多くは、対面点呼や遠隔点呼に切り替えることで対応できました。しかし、血圧やアルコール呼気濃度を計測し直しても許容範囲にならなかった場合等は点呼を完了させず、代理の運転手への交代や運行自体の中止に踏み切った例もありました。
こうしたケースは少数ですが、どの事業者にも起こる可能性があります。自動点呼から対面点呼・遠隔点呼へ切り替える、運転手の交代や運行の中止を判断する等、ケースに合わせた柔軟な対応が必要です。点呼がスムーズに完了しない場合を想定し、あらかじめ対応方法を明確に決めておきましょう。
なりすましへの対策が必要である
確実に本人であることを確認するための対策を講じ、なりすましを防止することも重要なポイントです。
業務前の点呼では、体温や血圧、アルコール呼気濃度等をチェックします。中でもアルコール呼気濃度は、飲酒運転による法律違反を防止する観点や、危険な運転による事故を防止する観点から、本人のものであるかを厳密に確認しなければなりません。
アルコールチェックのなりすましや身代わりによる不正は、これまでもいくつか発生しています。2024年には、郵便や物流を担う企業などによる不適切な点呼が行われていたことが明らかになっています。
運行管理者が直接チェックできない業務前自動点呼では、なりすましを防止する体制がとくに大切です。「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」には、点呼を行うための機器を設置する施設や環境についての次の条文があります(※6)。
(自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件)
第十条 業務前自動点呼機器又は業務後自動点呼機器を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに第八条各号に掲げる場所以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。
二 自動点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。
ドライバー本人が点呼を受けていることを確実にチェックするために、点呼の様子をビデオカメラ等で撮影することが、要件の1つとなっています。
なお、上記の「ビデオカメラその他の撮影機器」とは、点呼時に必要な事項を確認できる映像品質を備えたものであれば問題ありません。
【監修者コラム】業務前自動点呼、成功への鍵は「人」にあり
行政書士法人シグマ 代表行政書士 阪本浩毅氏
運輸業専門の許認可実務家・事故防止アドバイザー
現在導入が進められている業務前自動点呼システムは、日々の点呼業務に携わる運行管理者、運行管理補助者、貨物軽自動車安全管理者の皆様の負担を大きく軽減し、業務効率を飛躍的に向上させると期待されています。
これは、未来の運行管理に欠かせない画期的な取り組みです。
しかし、一方で、新しい機器の操作に慣れていないドライバーさんの中には、少なからず不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。せっかくの便利なシステムも、使いこなせなければその真価を発揮できません。
自動点呼の導入を成功に導くためには、システムそのもの以上に、ドライバーの皆様への丁寧な教育と手厚いサポートが不可欠です。
ドライバーを安心させるための具体的な取り組みをいくつかご提案します。
1. わかりやすいトレーニングの実施
機器の操作方法を解説する動画や、視覚的に理解しやすいマニュアルを用意し、誰でも安心して学べる環境を整えましょう。
2. 導入前の十分な練習期間
本番稼働の前に、実際に機器に触れて操作に慣れる機会を設け、疑問や不安を解消する時間を確保することが重要です。
3. 万全のサポート体制
導入後も継続して質問に答えられるサポート窓口や、よくある質問集(FAQ)を用意することで、ドライバーの「困った」をすぐに解決できるようにしましょう。
4. メリットの共有
自動点呼が、点呼の待ち時間短縮や出発時間の安定化など、ドライバー自身のメリットにも繋がることを積極的に伝えましょう。
ドライバーの皆様へのきめ細やかな配慮とサポートを通じて、自動点呼システムは円滑に導入され、運行に携わるすべての人にとって、より安全で快適な運行環境が実現されることでしょう。
業務前自動点呼にクラウドカメラが有効な理由
業務前自動点呼には、遠隔からでも点呼の様子をリアルタイムで確認できるクラウドカメラがおすすめです。正しい手順で点呼を実施しているか確認でき、なりすましの防止にも役立ちます。
なお、クラウドカメラの活用にはインターネット環境が必須です。操作性や画質についても確認し、自社に適したものを選びましょう。以下では、業務前自動点呼とあわせて便利に使える、おすすめのクラウドカメラを紹介します。
クラウドカメラなら「Safie One」がおすすめ
「Safie One(セーフィーワン)」は、工事不要で使い始められるクラウドカメラです。ねじ止めやライティングレールの使用により、天井に設置して撮影することも可能です。オプションのLTEドックを活用すれば、インターネット回線がない場所でも使い始められます。
録画した映像はクラウド上に保存されるため、離れた場所でもパソコンやスマートフォンから確認できます。運行管理者が現地にいない場合でも、リアルタイム映像を確認できるため、自動点呼だけでなく遠隔点呼にも役立つでしょう。

Safie
Safie One
エッジAIを搭載。画像解析による業務効率化も叶えるカメラ
¥50,600 (税込)
| 外形 | φ76.5×92.5mm |
| 重さ | 360g |
| 防水性能 | なし |
| ネットワーク接続 | 有線LAN、無線LAN |
| PoE給電 | 対応 |
| 画角 | 水平114° 垂直60° |
| ズーム | デジタルズーム 最大8倍 |
| マイク(音声入力) | あり |
| スピーカー(音声出力) | あり |
| 暗所撮影 | 対応 |
【注意】カメラの設置・運用にあたっては、事前にドライバーへの十分な説明と利用目的の通知を行うことが重要です。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
Safieは主要点呼システムと連携している
Safieのクラウドカメラは、次の主要な点呼システムと連携しています。
本記事執筆時点では、業務前自動点呼の運用開始に向けて業務前点呼機器の認定が進められています。上記の点呼システムも順次対応していく見込みですが、具体的な認定時期は各社により異なります。
いずれのシステムも業務前自動点呼の要件を踏まえた仕様となっているため、認定後には安心して活用できるようになります。Safieのクラウドカメラも併用することで、より確実な点呼の実現につながるでしょう。
業務前自動点呼で効率化と安全な運行を目指そう
業務前自動点呼は、本記事執筆時点では運用開始に向けて業務前点呼機器の認定の手続きが進められている段階です。運送事業者が業務前自動点呼を導入することで、点呼の確実性を高めつつ、運行管理者等の負担を軽減できます。業務を効率化することで、2024年問題の1つである労働時間の制限にも対応できるでしょう。
ただし、業務前自動点呼を運用していても、人による判断が必要となる場合もあります。アルコールチェックにおけるなりすましの防止対策も重要です。
自動点呼機器とともにクラウドカメラを導入することで、本人確認やドライバーの健康状態をよりスムーズにチェックできます。ただし、カメラの設置・運用にあたっては、ドライバーへの事前説明と適切なデータ管理を行い、プライバシーに十分配慮することが重要です。万全の態勢で業務前自動点呼を開始するために、ぜひSafieのカメラもあわせてご検討ください。
- いつでもどこでも映像が見られるクラウドカメラ
- スマホやパソコンから店舗・現場を見える化!
この記事の監修者
行政書士法人シグマ 代表行政書士
阪本浩毅(Sakamoto Hiroki)氏
一般社団法人日本事故防止推進機構 事故防止アドバイザー
都内の司法書士法人・行政書士法人にて企業法務に従事。行政書士として独立後は、運輸業専門として数多くの一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業に関する許認可法務に関与。現在は行政書士法人の経営を行いながら、運輸業の許認可法務の実務家として活動中。
※1 出典:“自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領”. 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課. 2024-05(参照 2025-07-15)
※2 出典:“業務前自動点呼の制度化に向けた要件の最終とりまとめについて”. 国土交通省.(参照 2025-07-15)
※3 出典:“乗務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめについて”. 国土交通省.(参照 2025-07-15)
※4 出典:“貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”. 国土交通省 関東運輸局. 2003-03-10(参照 2025-07-15)
※5 出典:“自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)”. 厚生労働省. 2022-12-23(参照 2025-07-15)
※6 出典:“対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示”. 国土交通省. 2025-04(参照 2025-07-15)
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。