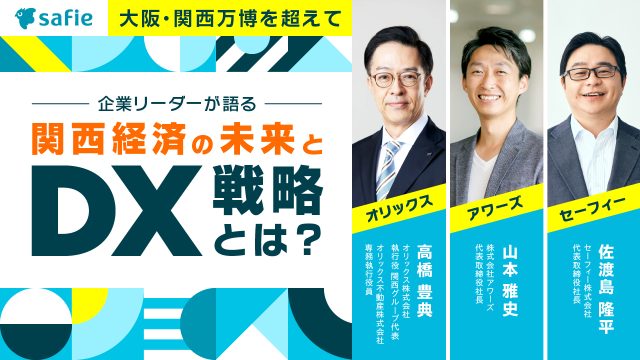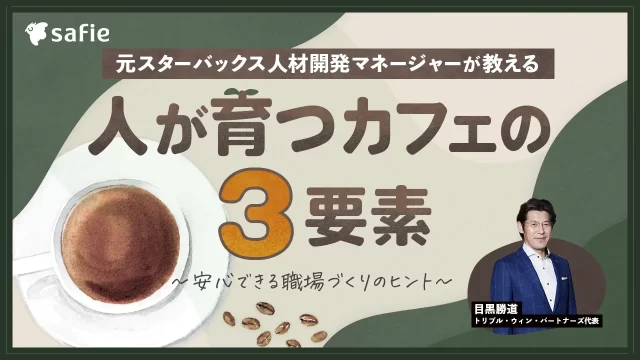建設現場の現場監督は、工事の進捗報告や適切な施工方法の証明などを目的に日々たくさんの工事写真を撮影する必要があります。撮り忘れを防止するための計画書作成や、再撮影をしなくて済むように、その都度チェックも欠かせません。今回の記事では、工事写真を撮る際の流れやコツを解説し、工事写真の撮影のためにカメラに備わっていると便利な機能もあわせて紹介します。
目次
工事写真を撮る目的
公共工事では、工事写真を撮影しておくことが義務化されています。一方、民間工事では義務付けられていないものの、工事写真はさまざまな報告や確認、証明、トラブル解決時の資料など多くの利用目的があります。
施工状況の記録
現場監督は、日常の作業や現場状況を記録して報告する必要があります。発注者側が完成後の建物を見ただけでは、適切な施工がおこなわれたのかどうかを判断できないためです。
建築物の施工は、「土木・建築・設備」など、複数の工程に分けて段階的におこなわれます。同じ建設現場に複数の下請け業者が入って施工をおこない、着工から竣工まで長期間に及びます。そのため、発注者に対する報告資料のための記録として工事写真が必要です。
設計図通りの仕上がり証明
設計図に基づいた仕上がりになっているかを証明するためにも、写真を記録します。建設工事では、設計図に基づいて施工を進めます。施工方法の仕様書や資材などはあらかじめ計画されているため、そのとおりに施工を進めなければなりません。
しかし、土のなかの基礎やコンクリート内の鉄筋などは、建物が完成したあとは見えなくなってしまいます。そのため、施工方法や使用材料が適切だったかを証明するために、途中経過をしっかりと記録しておく必要があります。
工事完了後の保全、維持管理の証拠
発注したお客様や下請け業者との間で万が一トラブルが発生した場合、施工方法などに問題がなかったのかを証明するものが必要です。その際に工事写真が証拠となり、トラブルを解決できることもあります。
建設物や施工内容など工事の責任がある人は、現場監督です。工事写真の記録が、現場監督を守ることにもつながります。
他工事の参考資料
建設業は、同じ建物・同じ下請け業者・同じ機材や資材という条件で建設するケースはほとんどありません。標準化が難しいため、写真が他の工事の参考資料として活用されることもあります。工事写真は、若手現場監督の教育や指導にも役立ちます。
工事写真の撮り方の基準
工事写真は、1枚のなかに明確な情報が伝わるようにする必要があります。どのような写真かがわかるように、情報を補足した「黒板」を一緒に添えて写真撮影をおこないます。黒板に明記する情報は、「5W1H」に基づいた内容でなければなりません。
【工事写真の黒板に記載する情報(5W1H)】
- When:いつ (撮影日・工事前後など)
- Where:どこで(工事場所・工事箇所など)
- Who:誰が(請負業者名・立会者名など)
- What:何を(工事名・工事種目・分類など)
- Why:なぜ・何のために(工事目的・規格・寸法など)
- How:どのように(施工方法・施工状況など)
これらの情報を黒板に記載して、対象物と一緒に撮影するのが基本的な撮影方法です。黒板に記載するフォーマットを決めておけば、記入する人により情報の過不足が出るリスクを防止できます。
工事写真を撮る基本的な流れ
工事写真を撮影する頻度は多いため、事前にどのような写真が必要かを確認し、撮り直ししなくて済むように撮影内容の都度チェックも必要です。ここでは、工事現場の写真撮影をスムーズに進めるための基本的な流れについて紹介します。
1.写真撮影の計画を立てる
施工に入る前に写真撮影の計画を立てて、撮影計画書を作成します。進捗状況や資材など写真撮影の機会は多いため、計画書がなければ写真の撮り忘れやミスが発生してしまいます。なにをいつのタイミングで撮影するのか、どのアングルで撮影するのかを整理し、計画書を作成しておくことでスムーズな撮影が可能です。
2.撮影機材の準備をする
次に、撮影するために必要な機材を準備します。デジカメのほか、最近ではスマホやタブレット、ウェアラブルカメラを使用するケースも増えています。スマホやタブレットは写真撮影やデータ保管、関係者との情報共有がひとつのデバイスでおこなえるため便利です。黒板をデジタル表示できるアプリなども登場しています。
ウェアラブルカメラは、身体に装着しながら撮影できるカメラです。データはクラウド上に保存できるタイプもあるため、別のデバイスからデータの視聴や共有が可能です。建設現場向けの防水・防塵・耐衝撃などの性能を備えたタイプもあります。
\防水・防塵・耐衝撃!建設現場向けのウェアラブルカメラ/
3.写真の撮影
撮影計画書に従い、写真撮影をおこないます。撮影する担当者を決めておき、実際の撮影は現場監督が立ち会い撮影します。被写体が中心になるようなアングルで、黒板は文字の内容がわかるよう近くに添えます。また、施工前と施工後のようすがわかるように、同じ位置での写真撮影が必要なものもあります。
4.その場で写真の確認をおこなう
撮影した写真は、その場ですぐに確認します。黒板の内容が確認できなかったり、不要なものが写り込んでいたりすれば、すぐに撮影し直します。撮影ミスがあったことにあとから気づくと、改めて撮影する手間が生じてしまい非効率的です。そのため、撮影写真は毎回しっかりと現場で確認することが大切です。
工事写真の撮り方のコツと注意点
工事写真は、工程が進んでしまったあとでは撮り直しができないこともあるため注意が必要です。起こりがちな失敗例を交えながら、撮り方のコツと注意点について解説します。
撮影計画をしっかり立てる
工事現場の写真は、なにを証明するものなのかにより対象物やタイミング、アングルなども異なります。また、工程が進んでしまうと再撮影できないものや、資材搬入の限られたタイミングで撮影しなければならないケースもあります。写真撮影のタイミングがずれてしまうと、作業員に迷惑をかけたり工期が伸びたりする恐れもあるため、必ず撮り忘れは防止しなければなりません。施工計画書を確認しながら、施工に入る前に撮影計画をしっかりと立てておきましょう。
撮影位置を固定する
建設現場全体を定点撮影する場合は、建物の完成後をイメージして撮影位置を決める必要があります。施工の変化がわかるように、なるべく同じ位置やアングルで建物全体が1枚に収まるように撮影しなければなりません。しかし、完成後をイメージせず定点撮影をおこなうと、完成後に全体が入りきらなくなったという失敗例がよくあります。とくに、高さや大きさのある建物を建設する場合は注意しましょう。
黒板の位置に注意する
黒板の位置にも注意が必要です。撮影する対象を中心にし、黒板が入るようにしなければなりません。定点撮影の際は、同じように撮影するために黒板の位置も決めておきます。
また、黒板の記載内容が太陽や照明に反射して見えないといった失敗もあります。内容が解読できなければ工事写真の意味がなくなるため、角度や明るさにも配慮した撮影を心がけましょう。
写真の編集はおこなわない
公共工事の場合、写真の編集は認められておらずそのまま提出する必要があります。国土交通省の「デジタル写真情報管理基準」により、工事写真は編集してはいけないと規定されています。
写真編集の例を一部紹介します。以下のような編集はすべてNGです。
- トリミング加工
被写体を大きく見せようとしたり、余計なものを取り除いたりするためにトリミングした。
- 画像の修正加工
黒板の文字が見えなかったり内容が間違ったりしたため、正しい内容に加工した。
- 画像の補正加工
逆光で見えない、暗いなどの理由から明るく見えやすいように補正した。
上記のような編集は、改ざんと捉えられます。工事写真は編集できないことを念頭に、写真計画と撮影後のチェックが大切です。
バックアップを取っておく
工事写真のデータは、バックアップをとっておきましょう。カメラやスマホなど本体やSDカードやUSBメモリなどの記録媒体を、破損・紛失させる可能性もあります。
バックアップを安心・スムーズにおこなうためにも、クラウドサーバーの利用がおすすめです。クラウドサーバーであれば、デバイスが壊れてしまってもデータは残っているため安心です。また場所や時間を選ばずに、複数のデバイスからデータの共有や確認ができるメリットもあります。
工事写真を撮る際にカメラに付いていると便利な機能
工事写真を撮影するカメラとしてデジカメを使用するケースや、近年ではタブレットやスマホに工事用のカメラアプリを入れて活用する方もいます。しかし、デジカメやスマホでの写真撮影は、建設現場ではデメリットとなる面もあります。たとえば、デジカメの場合は撮影したデータをパソコンなどに移す手間が必要となり、本体や記録メモリが破損すればデータを紛失してしまう恐れがあります。また、スマホは1台あればデータ確認や事務作業もこなせるメリットがあります。一方で、一人で作業と並行しながらの撮影や定点撮影が難しく、防水・防塵性能が弱いといった特性があります。
クラウドカメラやウェアラブルカメラであれば、ネットワークを通して遠隔地との連絡やデータ保存が可能であり、活用方法の幅が広がります。クラウドカメラやウェアラブルカメラのなかにも、さまざまな機能があります。そのため、以下で紹介する工事写真を撮影する便利な機能が備わっているものがおすすめです。
遠隔地からの指示
遠隔地からカメラの映像を確認しながら、指示を出せる機能が備わっていると便利です。クラウドカメラの場合、撮影したデータはクラウド上に保存され遠隔から映像をパソコンやスマホで確認できます。また、マイク機能が備わったクラウドカメラであれば、遠隔地からカメラを通して現場に写真撮影の指示出しができます。ウェアラブルカメラも撮影と同時に通話できるタイプがあります。
このようにカメラを通して遠隔地から指示を出せれば、若手監督者のサポートにも活用できます。ベテラン監督者が事務所や別の現場にいながら、映像を確認して指示やアドバイスをできるようになり、工事写真の撮影だけでなくさまざまな作業シーンで活躍します。
遠隔臨場モード機能
遠隔臨場とは建設現場に直接行かずに、ウェアラブルカメラやネットワークカメラの映像および音声を利用して、遠隔から「材料確認」「段階確認」「立会」をおこなうことです。国土交通省により現場の人手不足解消や働き方改革の推進などを目的に、作業効率を高めるため遠隔臨場が促進されています。
一方で遠隔臨場を実際した場合はいくつかの自治体において、遠隔臨場のようすを確認する画面に監督者を表示させた状態でのキャプチャー撮影が必要とされる場合があります。これは、遠隔から臨場をおこなったという記録を残すためのものです。
そのため、遠隔臨場の撮影時にカメラの管理画面に監督者をワイプ表示できる「遠隔臨場モード」機能があれば、管理画面をスクリーンショットするだけのため簡単です。反対に、このような機能がない場合は監督者が現場に行く必要がある、もしくは現場で別のタブレットなどで監督者のようすを表示させる必要があります。
スナップショットの保存
スナップショットは、パソコンやスマホ画面で視聴している映像からワンシーンを切り取り、JPEGなどの写真形式に保存する機能です。クラウドカメラ映像を視聴するための管理画面には、複数台のカメラを同時に確認したり、関係者にデータを共有したりできる便利な機能が備わっています。この管理画面にスナップショットの機能が備わっていれば、カメラの映像から必要なシーンを写真として保存できます。
必要な工事写真の取り忘れがあった場合でも、現場に設置しているクラウドカメラの過去映像を振り返り、必要なシーンをスナップショットで撮影するといった活用も可能です。現場に戻り再撮影しなければならない状況や、工事を中断しなければならないといった問題を防げます。
動画撮影時のスナップショットの撮影
カメラで動画を撮影している最中に、写真撮影ができるスナップショット撮影機能も便利です。遠隔臨場などで動画を撮影しながら同じカメラで写真撮影ができるため、現場作業員がカメラを持ち替えたり、撮影モードを切り替えたりする手間が必要ありません。
CALSモード
CALSモードとは、CALS/EC(公共事業支援統合情報システム)で推奨されている撮影モードに自動で切り替えできる機能です。CALS/ECは公共事業の効率化を図るため、従来は紙での情報提出だったものを電子化する取り組みです。
工事写真の電子データとして提出するための写真は、画質や画像サイズの基準が設けられています。カメラ機能にCALSモードがあれば、撮影データをそのまま使用できるためスムーズな撮影と業務の効率化が可能です。
防水・防塵・耐衝撃性
建設現場は、屋外作業であるため悪天候に耐えられる防水性能が必須です。また、建設現場の環境では、土やホコリなど過酷な環境にも耐えられる防塵性能も欠かせません。屋外使用に耐えられるものとして、IP66以上のものがおすすめです。
また、現場監督は動き回ることも多くカメラを地面に落下させたり、ぶつけたりする可能性もあるため、衝撃に耐えられる頑丈さも必要です。カメラ本体に衝撃から保護するカバーが備わっているタイプもあるため、耐衝撃性にも注意して選ぶようにしましょう。
\便利な機能を網羅!現場向けウェアラブルカメラ/
まとめ
工事写真の撮影は工程が進んでいると撮り直しもできず、写真自体の編集もできないためしっかりと計画を立てておくことが大切です。デジカメや近年では、スマホやタブレットを使用される方もいますが、写真撮影と報告をスムーズにするためにもウェアラブルカメラの導入がおすすめです。
セーフィーは映像ソリューションを提供している会社であり、クラウドカメラやウェアラブルカメラなどさまざまなカメラを扱っています。撮影した写真や映像はセーフィーのクラウドシステムに保存できるため、バックアップ環境も整っています。また、前項で紹介した工事写真を撮る際に便利な機能も備わっているため、工事写真の業務をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
- レンタルサービス「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」のご紹介
- 「Safie Pocketシリーズ」「Safie GO」の活用方法を事例を交えながらご紹介をしています。
※顧客や従業員、その他の生活者など人が写り込む画角での防犯カメラの設置・運用開始には、個人情報保護法等の関係法令の遵守に加え、写り込む人々、写り込む可能性のある人々のプライバシーへの配慮が求められます。防犯カメラとプライバシーの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「防犯カメラとプライバシーの関係。事業者が注意すべき設置のポイント」
※カメラの設置に際しては、利用目的の通知を適切に行うとともに、映像の目的外利用を決して行わないことが求められます。適切なデータの取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶「カメラ画像の取り扱いについて」
※ セーフィーは「セーフィー データ憲章」に基づき、カメラの利用目的別通知の必要性から、設置事業者への依頼や運用整備を逐次行っております。
※当社は、本ウェブサイトの正確性、完全性、的確性、信頼性等につきまして細心の注意を払っておりますが、いかなる保証をするものではありません。そのため、当社は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。